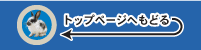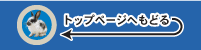NatureStudyから記事を一部紹介します。 NatureStudyから記事を一部紹介します。 |
| 2003年4号 |
ジュニア会員のページ |
山西良平 |
| 海べの似にたものどうし−タマキビガイのなかま− |
 ふつうの貝が住めないような海岸の高いところの岩場にいるのがタマキビガイのなかまです.大きさは数mmから1cmほどの小形の貝です.もともとは海の貝ですが,そこは、満潮のわずかな間だけ海水につかる場所なので,活動できる時間はみじかくて限られています.それ以外の間はじっとがまんして乾燥に耐えているのです.それだけでなく,夏の日照りのもとでは岩が私たちの手ではさわれないほど熱くなります.冬の夜の吹きさらしではこごえるほど冷たくなります.そんな所で,目には見えない小さな藻類を食べながら生活しているのです. ふつうの貝が住めないような海岸の高いところの岩場にいるのがタマキビガイのなかまです.大きさは数mmから1cmほどの小形の貝です.もともとは海の貝ですが,そこは、満潮のわずかな間だけ海水につかる場所なので,活動できる時間はみじかくて限られています.それ以外の間はじっとがまんして乾燥に耐えているのです.それだけでなく,夏の日照りのもとでは岩が私たちの手ではさわれないほど熱くなります.冬の夜の吹きさらしではこごえるほど冷たくなります.そんな所で,目には見えない小さな藻類を食べながら生活しているのです.
きびしい環境を乗りこえたタマキビガイたちは,他に競争相手の貝がいないので,海岸の高い所をひとり占めしています.
 さて,大阪湾や瀬戸内海の海岸では,タマキビガイ(図1)という種が必ずといってよいほどいます.海岸に下りるときには,この貝を踏まずに歩むことがむずかしいほどです.アラレタマキビガイ(図2)も,たいていタマキビガイといっしょにいます.これらは入り混じっていることが多いのですが,どちらかというと,アラレタマキビガイの方が海岸の高い所に分布しています.とくに,満潮時の水面よりも上の,もっぱら波しぶきを受けているような高さでは,アラレタマキビガイだけが見られるようになります.逆に波しぶきがほとんど立たない湾の奥や入江の中では,アラレタマキビガイは姿を消してしまいます.外海的な環境を好む種と言えるでしょう. さて,大阪湾や瀬戸内海の海岸では,タマキビガイ(図1)という種が必ずといってよいほどいます.海岸に下りるときには,この貝を踏まずに歩むことがむずかしいほどです.アラレタマキビガイ(図2)も,たいていタマキビガイといっしょにいます.これらは入り混じっていることが多いのですが,どちらかというと,アラレタマキビガイの方が海岸の高い所に分布しています.とくに,満潮時の水面よりも上の,もっぱら波しぶきを受けているような高さでは,アラレタマキビガイだけが見られるようになります.逆に波しぶきがほとんど立たない湾の奥や入江の中では,アラレタマキビガイは姿を消してしまいます.外海的な環境を好む種と言えるでしょう.
 さらに,イボタマキビガイ(図3)という,外海に面した海岸にだけ分布する種もいます.この貝は大阪湾や瀬戸内海ではめったに見られません. さらに,イボタマキビガイ(図3)という,外海に面した海岸にだけ分布する種もいます.この貝は大阪湾や瀬戸内海ではめったに見られません.
タマキビガイとアラレタマキビガイとは,貝殻の形がとてもよく似ていて,見分けるには,少しトレーニングが必要です(博物館発行のミニガイド「大阪湾の磯いその貝」を参考にしてください).
アラレタマキビガイが住めない湾の奥や入江の中,そして干ひ潟がたができるような環境には,マルウズラタマキビガイ(表紙下)が姿を現わします.タマキビガイといっしょにいることが多いのですが,河口域のようなタマキビガイがいなくなる環境でも,マルウズラタマキビガイは生活できます.
波当たりや塩分濃度などの海岸の環境は,外海から内湾,河口へと移るにつれて変化します.瀬戸内海や紀伊半島の海岸では,その変化にともなって,外から順にイボタマキビガイ→アラレタマキビガイ→タマキビガイ→マルウズラタマキギガイというふうにタマキビガイ科の種が重かさなり合いながらの入れかわっていきます.
<山西良平:博物館学芸員>

|