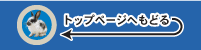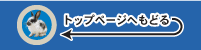NatureStudyから記事を一部紹介します。 NatureStudyから記事を一部紹介します。 |
| 2003年7号 |
ジュニア会員のページ |
石井久夫 |
| オオシャコガイの化石 |
 シャコガイのなかまは,サンゴ礁しようにすむ大きな二枚貝です.海岸には,波でうちあがったシャコガイの貝殻かいがらがたくさんころがっていることもあります.生きたシャコガイは,日本では,沖縄おきなわの海で見ることができます.グラスボートから海中のサンゴ礁をのぞいたとき,サンゴの中にあざやかな色で複雑ふくざつなもようのシャコガイを見たことはありませんか.その色はシャコガイの色ではなく,貝の外がいとう膜まくにすむ藻類そうるいの色です.シャコガイはこの藻類から栄養えいようをもらっているのです.ところで,シャコガイの生きているときの姿を実物や写真で見て,どこかへんだな,と思いませんか.シャコガイは貝殻のおなか側を上に向けて生活しているのです(図1).藻類にたくさん陽があたるようにしているのでしょう.おなか側の外とう膜は藻類の畑のようです.
シャコガイのなかまは,サンゴ礁しようにすむ大きな二枚貝です.海岸には,波でうちあがったシャコガイの貝殻かいがらがたくさんころがっていることもあります.生きたシャコガイは,日本では,沖縄おきなわの海で見ることができます.グラスボートから海中のサンゴ礁をのぞいたとき,サンゴの中にあざやかな色で複雑ふくざつなもようのシャコガイを見たことはありませんか.その色はシャコガイの色ではなく,貝の外がいとう膜まくにすむ藻類そうるいの色です.シャコガイはこの藻類から栄養えいようをもらっているのです.ところで,シャコガイの生きているときの姿を実物や写真で見て,どこかへんだな,と思いませんか.シャコガイは貝殻のおなか側を上に向けて生活しているのです(図1).藻類にたくさん陽があたるようにしているのでしょう.おなか側の外とう膜は藻類の畑のようです.
 シャコガイのなかでもオオシャコガイはとくに巨大で,殻の長さは1m以上,重さは200kgを超えることがある,貝のなかでも最重量級です.図ず鑑かんには,すんでいる海は沖縄以南と書かれていますが,沖縄県の八や重え山やま諸島しよとうでもたいへん珍しく,近年,宮古島で生きた個体がみつかった,というぐらいです.ところが,貝殻だけは,海岸の波打ち際でときどき見つかるそうで,図2の写真は,西表島の砂浜で,なかば埋もれていた貝殻です.貝殻の表面のようすから古い時代の化石のようでした.見えている部分だけで60cmを超えていたので,掘り起こして持ち帰るのはあきらめました.
シャコガイのなかでもオオシャコガイはとくに巨大で,殻の長さは1m以上,重さは200kgを超えることがある,貝のなかでも最重量級です.図ず鑑かんには,すんでいる海は沖縄以南と書かれていますが,沖縄県の八や重え山やま諸島しよとうでもたいへん珍しく,近年,宮古島で生きた個体がみつかった,というぐらいです.ところが,貝殻だけは,海岸の波打ち際でときどき見つかるそうで,図2の写真は,西表島の砂浜で,なかば埋もれていた貝殻です.貝殻の表面のようすから古い時代の化石のようでした.見えている部分だけで60cmを超えていたので,掘り起こして持ち帰るのはあきらめました.
今の八重山諸島あたりはサンゴ礁が大きく広がり熱帯の海と思いますが,オオシャコガイにとっては北限ほくげんで,本来はもっと暑い海のほうがすみやすいようです.では,波打ちぎわでオオシャコガイが見つかるのはなぜでしょう.これらのオオシャコガイは,大部分が今から数千年前に生きていたものだと考えられています.そのころは本土では縄文じようもん時代にあたり,今より数m海面が高く温暖おんだんだった時期です.沖縄の海も今より熱帯的だったのでしょう.そのころ生きていたオオシャコガイの化石が,大きな波に運ばれて今の海岸に打ち上がったものと考えられます.
それにしても図2のオオシャコガイは,もっと化石らしい感じがします.近くの崖がけを見ると,琉球石灰岩りゆうきゆうせつかいがんという数万年よりも古い時代のサンゴなどからできた地層がありました.このオオシャコガイは琉球石灰岩から転げ落ちて今の砂浜に埋もれたものだと推定できました.数千年まえよりもっと古い時代にも,オオシャコガイがすみやすい暑い時期があったのだと思いました.
<石井久夫:博物館学芸員>
図1.自然史博物館第3展示室のオオシャコガイ.腹縁(おなか側のへり)が上を向いている.
図2.オオシャコガイの化石.
|