


(1)Volvoxの光走性に影響するイオンチャンネルの温度依存性とイオン濃度 竹林 隆昭(興国高校)
Volvox aureus は、低温状態で光を当てると、カチオン濃度が高い場合は光より逃げるが、低い場合は
逆の反応を示す。これは、温度依存性のイオンチャンネルが低温(9℃)で影響していると思われる。
この一つがナトリウムチャンネルではないかと調べてみた。
(2) 新学校設定科目「生命論(環境)」 森中敏行(大教大附高校天王寺校舎)
昨年度の問題点を改善するため、取り入れた以下の実践と問題点を報告。
① 生徒への事前講義およびレポート課題を取り入れた。
② 地元の自然学校(NPO)に実施意図を説明し、現地での実施主体になっていただいた。
③ 各プログラムの統合化を図るため、大阪教育大学理科教育環境教育研究室の協力をいただき、
大学院生にも参加いただき、コンセプトマップを現地で作成した。
(3)飼い鳥の遺伝―45年間の飼育暦から― 北村 正信(府立鳥飼高校)
セキセイインコの体色や鑑賞用ハトの羽毛の生え方(メンデル遺伝)、オカメインコの模様(伴性遺伝)、
頭部の羽毛がカッパ状になる(致死遺伝)等を写真を中心に報告。
(4) ブタ胎児を用いた解剖実習の実践(中間報告) 上久保真理(府立豊中高校)
本校でブタ胎児を用いた解剖の実習を実践して3年目になる。その意義と方法・結果について報告。
本実習は動物の体を理解するために、とても有効かつ簡単に実施できるものである。
(5) デジタル教材活用の共同研究 広瀬 祐司(府立茨木高校)・中根 将行(府立高津高校)
デジタル教材を使用した授業を体験した生徒群(茨木高校)、していない生徒群(高津)に対して、同一
アンケートによるデジタル教材に対する有効性評価を実施した。体験群では、非体験群に対してデジタル
教材に対する評価が高かった。茨木高校では、それに引き続き実験とデジタル教材による授業を一体化
させた授業を試行し、公開した。
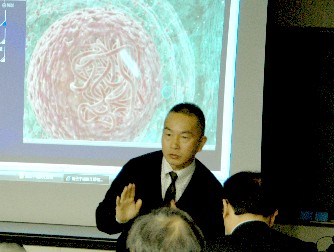

 (6) 学校設定科目「生命科学」における教材開発 片山 徹(府立枚方なぎさ高校)
(6) 学校設定科目「生命科学」における教材開発 片山 徹(府立枚方なぎさ高校)『生命科学』で使用することを主たる目的として、開発してきた「聴診器の歴史」「心臓・AED」「糖尿病の
歴史」「種痘の歴史」「ウィルスの発見」「新型インフルエンザ」「野口英世物語」などの授業実践と今後の
課題について。
(7) 学校設定科目「環境科学」における実践と反応 片山 徹( 同 上 )
『環境科学』で取組んでいる様々な実践―「環境教育」「ゴミと環境」「eco検定」「プロジェクト・ワイルドの
アクティビティ」「環境放射能測定」「NIE」「エネルギー環境教育」など―の報告と生徒の反応について。


