大阪府立堺上高等学校 橘 淳治
はじめに
ここでは、湖や川での水質調査の概要について説明します。水質調査と言っても、魚、プランクトン、ベントス(底生生物)や水生昆虫を中心とした生物調査、水温、濁り、流速を中心とした物理調査、窒素やリンを中心とした化学調査など色々あります。
水質調査を行う前に
水質環境の調査だけではなく、すべての野外調査に共通して大切なことは事前調査です。事前調査は、過去の調査結果が書かれた文献を見るほか、最も大切なものは地図(特に地形図)による調査地点の検討です。
河川や湖沼の調査では、地形図によりその水域の特徴的な地点や代表的な地点をあらかじめ考えておき、また、その地点への進入路を調べておくと調査当日の作業がスムーズに進めることができます。
水質調査項目の意味とその方法について
水質調査を進めるにあたって多くの調査項目が考えられますが、その項目の意味を知ることは大切です。色々な調査には必ず目的があるはずなので、その目的に則した水質調査項目を選んで調査をします。
以下に、代表的な水質調査項目の意味と方法を示します。
1,生物調査
①植物プランクトン調査
植物プランクトンは水界の一次生産者(光合成をする植物)として生物生産の立場から重要であるばかりでなく、植物プランクトンは水質の影響を受けて種組成が変ることが多いので、生物指標としても重要です。植物プランクトンは一般に小型のものが多いので、プランクトンネットではごく一部しか集めることができません。従って、プランクトンネットで採集を行うときにはこの点を十分知っておく必要があります。
定量的に調査を行うには、採水器やバケツを用いて採水し、その試水をポリエチレンビンに入れます。そして、市販のフォルマリンを、試水1000mlに対して10ml程度入れて固定します。それを静置すると植物プランクトンは沈んで底に溜まるので上澄みを静かに捨て、100ml程度のメスシリンダーに植物プランクトンを含む試水を入れて再び静置します。さらに、同様の操作で上澄みを捨てて最終的に10ml以下にします。この試水に対して検鏡を行ない、試水1l当たりの個体数(群体を形成するものではコロニー数)で表現します。
大雑把な方法でありますが、植物プランクトンの沈殿量(ml)で植物プランクトンの量を表わすこともあります。
植物プランクトンのうち、鞭毛藻類などはフォルマリンで固定すると壊れたり、変形したりするので、個体数が多い場合には、試水をそのまま検鏡したほうがよいことがあります。
定性的な調査でもこれとほぼ同じ操作を行ないますが、大型のものを見るだけであるならプランクトンネットを用いて採集した試料を直接検鏡してもよろしい。
②動物プランクトン調査
動物プランクトンは一次消費者として重要であり、また、呼吸の関係上、溶存酸素やその他の水質の影響を受け種組成が変化しやすいので生物指標としてよく用いられます。一般に植物プランクトンに比較して大型のものが多いので、プランクトンネットを用いて採集します。
定量採集は、NXX25程度のメッシュのプランクトンネットを用いて行ない、プランクトンネットの口径とネットを曳いた距離から濾過量を計算しておきます。ネットで採集したプランクトンは、100mlに対して5mlの割合でフォルマリンを加えて固定します。この試水に対して検鏡を行ない、試水1l(または1m3)当たりの個体数で表現します。
定性採集も定量採集とほぼ同様の操作で行なうが、検鏡したときに主要な種を中心に多い少ないで記述します。
③付着藻類調査
河川では、一次生産者としては付着藻類が生産量の大半を占めるの重要であります。付着藻類は、川底の石などに付着したものを、歯ブラシなどで一定面積を剥がし落とし、それを少量の水と共にサンプルビンなどに入れ、フォルマリンで固定して検鏡します。フォルマリンの量は付着藻類の量によって異なるが、試料20mlに対してフォルマリンを1ml程度入れ、検鏡します。結果は付着面積1c㎡当たりの個体数で表わす。
大雑把な方法でありますが、植物プランクトンと同様に、10ml程度のメスシリンダーや沈殿管に試料を入れて静置し、沈殿量で表わすこともあります。
④底生生物調査
消費者として位置付ける場合と分解者として位置付ける場合があります。エックマンバージ採泥器などを用いて底泥と共に採取し、サーバーネット等で泥の中から生物をより分けます。貝類、ユスリカ、イトミミズ類などがこれに属します。フォルマリンで固定して持帰り、図鑑などを参考に同定します。
定量採集は難しく、コアーサンプラー等を用いて泥を柱状に採取する必要があります。
⑤水生昆虫調査
水生昆虫は高次の消費者の位置にあります。水生昆虫は種により呼吸量や餌の取り方に差があるので、水質(特に溶存酸素)や水温のほか、有機汚濁物質に対する耐性も様々です。そのため水質汚濁の生物指標として古くから用いられています。
ふつう、1m×1mのコドラートを水中に作り、そこに生息する水生昆虫を集めてフォルマリンで固定して持帰り、図鑑や標本を参考にして同定します。
⑥魚類調査
魚類の多くは2次~3次消費者の位置にあるあります。魚類は漁業と関連し、生物生産の立場から調査が行われることが多いです。魚類の捕獲方法は、刺し網、投網、モンドリなど多くの方法があるので、方法により捕獲される魚種が異なるので調査結果を見るときはこの点にも注意します。
魚類の定量調査は一般的には難しいです。
⑦水生植物調査
湖沼などでは水草等の沈水植物、ヨシなどの抽水植物は生産者として重要であるばかりでなく、直接的に水質に影響を与えるため調査することは重要です。また、湖岸の陸上植物も枯死したときに分解して有機物を湖沼に供給する等のことから、水質に影響を与えるので調査する必要があります。
2,物理調査
①水温
水の物理的な性質を知る最も基本的な項目であります。湖沼では、水温を調べることにより成層状態を知ることができるほか、河川やダム湖では水の混合状態などを知る手掛かりとなります。
一般的にはサーミスター温度計を用いて測定しますが、50℃までの棒温度計を用いてもかまいません。
②水色(すいしょく)
河川や湖沼の色を変化させる原因としては、光、周囲の植生、湖水中の浮遊物、溶存物質、浅い場合は底質などが考えられます。これらが影響を与え合いながら特有の水色を呈します。
特に富栄養化の進行した水域では植物プランクトンの増殖が盛んなため、浮遊物の大半を植物プランクトンが占めます。そのため、水色から植物プランクトンの大まかな分類(ラン藻類、珪藻類、緑藻類)が分ることがあります。ラン藻類が多い時は青緑色、珪藻類が多い時は茶色、緑藻類が多い時は緑色の水色を呈します。
フォーレル・ウーレの水色計による判定が一般的です。
③透明度
透明度は湖沼の濁度(水の濁りの原因になる粘土などの無機物、プランクトンやその遺骸等の有機物の量に関係します)、水中照度(透明度の深度での水中照度は水面の照度の15%になります)、補償深度(水中の微生物群集の呼吸と光合成が等しくなる照度にあたる深度で通常透明度の2~2.5倍の深度に相当します)、沈水植物群落の生育下限深度(最も低照度で生育可能な水草である車軸藻の生育限界の深度が透明度に相当し、この深度より浅いところを沿岸帯、深いところを沖帯としています)、湖沼型分類(透明度が4m以下を富栄養湖、8m以下を中栄養湖、8mを越えるものを貧栄養湖)の推定に用いられます。
セッキー円板(直径25cm~30cmの白色円板)で測定し、その円板を沈めていき、見えなくなる深度で表わします。
④透視度
透明度は現場の環境で測定するのに比べ、透視度は採水した水そのもの濁度の推定に用いられますが、透明度ほど一般的ではありません。簡単な器具で測定できるのでしばしば用いられます。
直径2.5cmで高さが30cm~45cmの円筒状の透視度計に試水を入れ、筒の底にある大きさ1.75mmの活字が判読できなくなる試水の高さ(cm)で表現します。
3,化学調査
①電気伝導度
水中のイオンの量により電気伝導度は著しく変化しますので、ナトリウムイオン、マグネシウムイオン、塩化物イオン等の主要イオン量を知る手掛かりとして用いられる他、河川水、地下水その他、異質の水の流入状況を簡単に知る手掛かりとして用いられます。
電気伝導度計で測定し、電気伝導度は水温によって変化するため18℃の水温における値に換算したものを用います。μS/cm(マイクロジーメンス毎センチメートル)で表現します。
②pH(水素イオン指数)
pHは、集水域(水が流れ込む地域)の地質からの溶存成分や、大気中に約350ppm存在する二酸化炭素の溶解、植物の光合成や微生物の呼吸や分解による水中の二酸化炭素の増減に伴う水素イオンの平衡が移動することにより変化するため、水中のpHの値はよく変化します。
蒸留水のpHは大気中の二酸化炭素の溶解によりpHは5.6ですが、ふつう、淡水湖では種々のイオンが溶解しておりpHは7付近です。最近は、pH5.6以下の雨である酸性雨の影響により、諸外国では酸性化した湖沼が増えています。
pHの測定はガラス電極pHメーターや比色計によって測定します。学校などでは共立理化学研究所から発売されている、簡易比色用の「パックテスト」を使うと簡単に測定できます。
③DO(溶存酸素量)
溶存酸素量は、温度、塩分などの溶存成分により決まり、温度が高いほど、また、塩分濃度が高いほど水中の溶存酸素量は減少します。一般的に河川の上流部の流水では溶存酸素はその水温においてほぼ限界まで溶けており、飽和度は100%近くになります。
静水域での溶存酸素量の増減は、主に植物の光合成により増加し、逆に動植物の呼吸や微生物による有機物の分解により減少します。
魚類をはじめとする水生生物は呼吸のため酸素を必要とするので、溶存酸素量が少ないと生存できません。そのため、漁業の立場から溶存酸素量は測定されることが多いようです。また、静水域では溶存酸素の減少の主な要因は有機物の分解によるものであるため、有機汚濁の一つの指標としても古くから測定の対象になっています。
溶存酸素の測定は、ウインクラー法や溶存酸素計で測定し、mgO2/l、ppmや飽和度(%)で表わします。学校では、共立理化学研究所から発売されている、アンプル式の簡易比色キットの「ケメット」を使うと測定できます。
④Na+(ナトリウムイオン)
ナトリウムイオンは、陸水中の主要成分の一つであり、海岸近くでは海からの風送塩によって、また、内陸部では岩石や土壌等からの溶出によって河川や湖沼に供給されます。従って、河川や地下水ではその水の起源を知る手掛かりとして測定することがあります。また、塩化物イオンと同様に、産業活動や日常生活で塩化ナトリウムを排出するので人為汚染の指標としても用いらます。
測定は炎光光度法、原子吸光法、イオンクロマト法やICP発光分析で行ない、測定結果はmgNa/lで表現します。
ナトリウムイオンは比色法では測定が出来ないので、簡易比色キットなどがありませんの学校で測定することは困難です。
⑤K+(カリウムイオン)
カリウムイオンは窒素、リンと並ぶ植物の3大栄養素として重要です。陸上植物ではカリウムイオンは不足することが多いが、水中の植物にとって不足することは殆どありません。水圏への主な供給源は岩石や土壌の溶出と考えられるが、田畑にまかれた肥料などからも供給されることも多いようです。他の主要成分(陽イオン)に比べて季節変動が大きく、これは生物の影響によるものと考えられています。
測定は炎光光度法、原子吸光法、イオンクロマト法やICP発光分析で行ない、測定結果はmgK/lで表現します。ナトリウムイオン同様、比色法では測定が困難なので適当な簡易比色キットなどがありません。従って、学校で測定することは難しいようです。
⑥Ca2+(カルシウムイオン)
カルシウムイオンは、石灰岩等の岩石から溶出される成分で、河川による差が大きいです。日本の河川では5~20mgCa/lのものが多いです。地下水ではCa2+の濃度は非常に高い傾向があります。生物の作用で変化することは殆どないぐらい水中には十分に存在しますので、河川や湖沼で測定する目的は水の流入や流出の径路を推定のためです。
測定は、EDTAによる滴定法のほか、原子吸光法やイオンクロマト法で行ない、測定結果はmgCa/lで表現します。学校では、共立理化学研究所から発売されている簡易滴定法の「ドロップテスト」を使うと、簡単に測定できます。
⑦Mg2+(マグネシウムイオン)
マグネシウムイオンもカルシウムイオンと同様に岩石や土壌から溶出される成分ですが、海岸近くでは海からの風送塩による供給も多く見られます。水中には豊富に存在するため、生物の作用によって現存量が変化することは殆ど見られません。測定の主な目的は河川や湖沼水の起源を知る手掛かりにすることです。
測定は、EDTAに滴定法のほか、イオンクロマト法を用い、測定結果はmgMg/lで表現します。学校では、簡易滴定法や簡易比色法でも測定できます。
⑧Fe(鉄)
水中における鉄の存在形態は大変複雑で、pHや溶存酸素の量によって形態を変えることが多い。一般に難溶性(不溶性)のものとして無機粘土粒子中の鉄、生物体中の鉄および鉄の水酸化物があり、可溶性のものとして鉄イオン(Fe2+とFe3+)、錯体(鉄錯イオン、錯化合物)があります。
水中の鉄の測定と言えば、一般的には酸可溶性鉄のことで、水中に存在する総ての鉄のうち塩酸酸性で溶解して鉄イオンとなって測定できるものをさします。
鉄は湖沼の酸化還元状態を知るために、多くの場合マンガンなどと共に測定します。酸化的な環境では鉄は三価(Fe3+)、マンガンは4価(Mn4+)になり、これらのイオンは不安定なのですぐに不溶性の水酸化物になります。また、還元的な環境では鉄は二価(Fe2+)、マンガンも二価(Mn2+)になり、可溶性のイオンとして存在しますので、湖沼環境を知る重要な手掛かりになります。
オルトフェナントロリンによる比色法で測定し、測定結果はmgFe/lで表現します。
⑨Cl-(塩化物イオン)
生物による変化を受けにくいイオンですが、ヒトの生活や産業活動によって自然界に排出されることが多いので、人為汚染の指標となるものであります。また、海岸近くの湖沼では海からの風送塩の供給の程度を知る手掛かりとなるほか、河川においては温泉水や海水の流入状況を推測する手段として用いられることがあります。
濃度が高い場合は塩化銀滴定法を、また、濃度の低い場合はチオシアン酸水銀による比色法を用いて測定し、測定結果はmgCl/lで表現します。
⑩アルカリ度
アルカリ度は水に含まれている重炭酸塩、炭酸塩及びケイ酸塩等の弱酸塩の総量を中和するのに必要な酸の当量数で表わすもので、pH4.7にするときの値を使うことが多いです。一般に天然水は重炭酸塩と少量の炭酸塩を含んでおり、アルカリ度が高いと、その天然水は緩衝能力が大きいことを意味しています。
さらに、二酸化炭素が水に溶解すると酸性を示すので、土壌のカルシウムやマグネシウムはそれぞれCa(HCO3)2、Mg(HCO3)2となって溶解するので、アルカリ度はカルシウムイオンやマグネシウムイオンの濃度と比例の関係を持ち、土壌や岩石の風化の程度を推定する指標ともなります。[次式参照]
CO2 + H2O → H2CO3
→ H+ + HCO3- → H+
+ CO32-
↓
Ca → Ca2+
Mg → Mg2+
また、有機物の分解に伴い二酸化炭素が発生しアルカリ度が高くなるので、有機汚濁の指標としても用いられることがあります。
測定は、0.02N硫酸滴定法(pH4.7)で行ない、測定結果はmg当量/lで表現するほか、HCO3-に換算し、mgHCO3-/lで表わすことも多いです。
⑪NH4+-N(アンモニア態窒素)
河川・湖沼における植物の増殖の制限因子としては窒素、リン、ケイ素があり、これらはまとめて栄養塩と呼ばれます。
アンモニア態窒素は、植物の窒素源として最も重要です。アンモニア態窒素は有機物の分解過程で最初に生成される無機態窒素なので、有機汚濁の進行した水域ではその現存量が高く、有機汚濁の指標としても用いられることが多いです。
測定はインドフェノール法による比色分析で行ない、測定結果はμg-at.N/l(または、μmol/l)で表現します。
⑫NO2-(亜硝酸態窒素)
アンモニア態窒素の硝化により生成されるもので、これはさらに硝化されて硝酸態窒素になります。すなわち無機態窒素の中間代謝物であるため一般にその現存量は他の無機態窒素に比較して小さいです。しかしながら、有機汚濁の進行した水域ほどその現存量は高い傾向があるので、河川では測定することが多いです。
測定は、N-1-ナフチルエチレンジアミン法による比色分析で行ない、測定結果はμg-at.N/l(または、μmol/l)で表現します。
⑬NO3-(硝酸態窒素)
無機態の窒素栄養塩の中で、酸化的な環境で最も安定に存在する化合物です。従って、上流の河川水のように酸素の供給が多く、動植物の活性の比較的低い水域では無機態の窒素に占めるその割合は高いです。
測定はカドミウム-銅カラム還元法による比色分析で行ない、測定結果はμg-at.N/l(または、μmol/l)で表現します。
⑭PO43-(リン酸態リン)
河川や湖沼の植物にとっては窒素以上に増殖の制限因子になりやすいもので、水中での存在形態はオルソリン酸であると考えられています。近年、富栄養化の原因物質として重要視され、リンを結合剤に含む合成洗剤の使用を禁止したり、下水処理では高次処理でリンを除いたりしています。
測定は、アスコルビン酸還元のリン-モリブデン錯体による比色分析で行ない、測定結果はμg-at.P/l(または、μmol/l)で表現します。
⑮SiO4-Si(ケイ酸態ケイ素)
ケイ酸態ケイ素は珪藻の殻の形成に必要なため、栄養塩に入れられることがあります。水中での存在形態も複雑で未解決の部分が多いですが、オルソケイ酸かメタケイ酸であると考えられています。
また、この現存量は地質により決まるので、水域の水の起源を知る手掛かりとしてもしばしば用いられます。
⑯BOD(生物化学的酸素要求量)
河川水や湖沼水などの有機汚濁の程度を示す指標となるもので、水中の有機物を微生物によって分解させるときに必要な酸素の量から求められます。これは、水中の有機物量が多いほど分解させるのに多量の酸素を必要とする原理を利用したものです。
測定は20℃にて5日間微生物によって試水を分解させ、その時に消費した溶存酸素の量(mgO2/l)で表現します。
⑰COD(化学的酸素要求量)
海水などの有機汚濁の程度を示す指標となるもので、水中の有機物を過マンガン酸カリウムや重クロム酸カリウム等の酸化剤によって分解させるときに必要な酸素の量から求めます。これは、水中の有機物量が多いほど分解させるのに多量の酸素を必要とする原理を利用したものです。
CODは、用いる酸化剤の種類や酸化条件によって値が異なるので、必ずこれらの条件を明記する必要があります。また、BODとも高い相関があるのでBODを測定する代わりにCODで代用することもあります。
測定結果は、試水を酸化分解するときに要した酸化剤の量より酸素の消費量を求め、mgO2/lで表現します。
⑱SS(懸濁物質)
水の濁りの原因となる物質の総量を表わすもので、通常孔径1μmの濾紙で捕捉される物質です。水中の懸濁物質は、土壌の流出による粘土鉱物などの無機物質とそこで生産されたプランクトン(主に植物プランクトン)によってその現存量が決まります。
測定は、試水を孔径1μmのグラスファイバー濾紙で濾過して捕捉された物質の乾燥重量計る方法で行ない、測定結果はmg/lで表現します。
⑲クロロフィル量
一次生産者である植物プランクトンの現存量を表わすものとして用います。また、植物のクロロフィルは分解を受けるとフェオフィチンに変化するので、クロロフィルとフェオフィチンの比率から植物プランクトンの活性を推定することができます。
測定は、孔径1μmの濾紙上に捕捉された懸濁物からアセトンでクロロフィルを抽出し、吸光光度法や蛍光光度法で計るほか、最近では高速液体クロマトグラフ等を用いることもあります。測定結果はμg-chl.a/lで表現します。
3、調査結果とまとめ
水質調査のまとめは、調査の目的と調査方法の意味をよく考え、調査結果(実測データ)をもとに客観的に表現する必要があります。また、河川や湖沼の水質の季節や時間的な変動は大きいので、1回だけの調査で判断するのは危険が伴うので、通常は数回の調査を行なって総合的にまとめる必要があります。
参考文献
河合章、杉田治、出口吉昭(1988):水族環境学実験、恒星社厚生閣.
小山忠四郎、半田暢彦、杉村行勇(1972):湖水・海水の分析、講談社サイエンティフィック.
西条八束(1957):湖沼調査法、古今書院.
西条八束、三田村 緒佐武(1995):新編湖沼調査法、古今書院.
鈴木静男(1994):水の環境科学、内田老鶴圃.
堰根勇(1973):水の循環、共立出版.
津田松苗(1962):水生昆虫学、北隆館.
角皆静男(1972):雨水の分析、講談社サイエンティフィック.
日本水質汚濁研究協会(1982):湖沼環境調査指針、公害対策同友会.
萩原耕一、佐藤正光、上野景平、中原啓司、田端健二(1986):簡易水質試験法、共立出版.
浜島繁隆(1979):池沼植物の生態と観察、ニューサイエンス社.
半谷高久、小倉紀雄(1985):水質調査法改訂第2版、丸善.
三宅泰雄、北野康(1976):唇水質化学分析法、地人書館.
T.R.パーソンズ、高橋正征(1979):生物海洋学、三省堂.
このホームページに関するご意見、ご感想は E-mail:
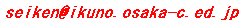 までお願いします。
までお願いします。