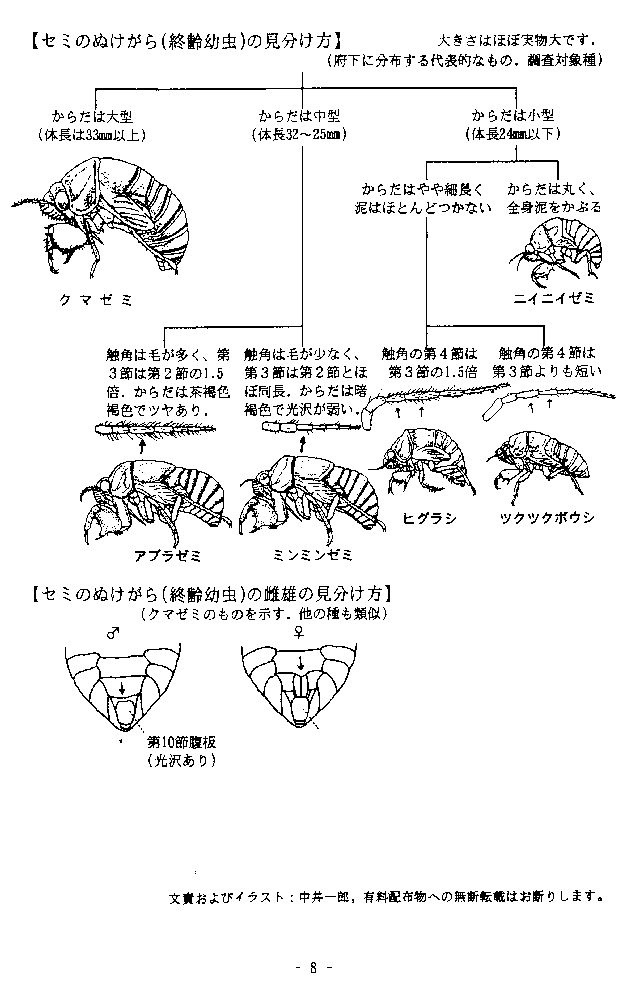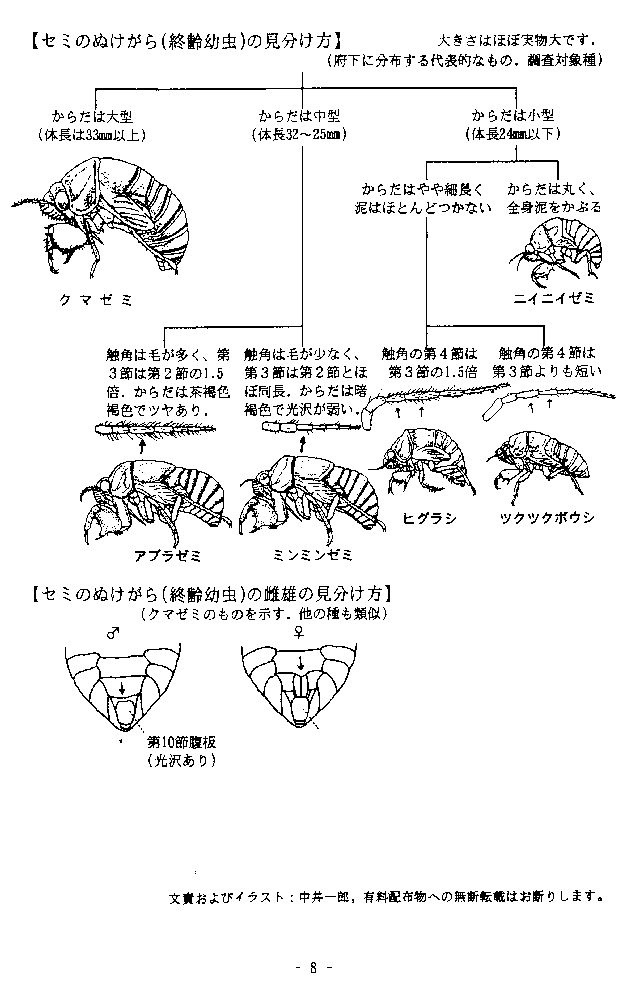大阪府高等学校生物教育研究会
セミのぬけがら調査実施要領

- <目的>府下の各地点で、ほぽ同じ時期に同じ方法で、温度環境の指標となるセミ類の分布状況を知ることによって、府下の温度環境の把握をめざす。これによって都市部のヒートアイランド化の状況を大づかみするとともに、将来にわたって調査を継続することによって、温度環境の変化を見つめ続けたい。
- <実施方法>大阪府の主な公園について、高校の生物部あるいは生物科教職員の手で、環境指標となるセミの調査を、ぬけがらを調ぺる方法で行う。調査地点1校の生物部あるいは教職員(教職員グループも可)に、原則として学校およぴ学校周辺・自宅周辺の公園(原則として5000m2以上の公園)を調査する。郊外のキャンプ場や野外活動施設での調査でも結構です。事前調整は行わないので、1校・1人で何地点調査してもよい。調査対象セミのぬけ殻のみを対象とする。これは、ぬけ殻の存在が、
- その場所で雌雄個体が存在し繁殖・産卵が行われたこと、
- 餌・無機的環境などがその種の卵から成虫にいたるまでの条件をクリアしていたことを示唆するからである。
移動性の高い成虫の分布よりも移動性のほとんどない幼虫期の分布の方が環境指標として適切である、なお、無用に生物を殺さなくてすむという利点もある。
- 調査時期
7月25日〜8月10日とする。時期によって発生するセミの種類やその割合が変化するので、時期を統一する。個々の調査日は各校・各自決めてよい。
- 調査方法
- 調査地点で無作為に20分間(調査者数が3名以上の場合は15分)採取可能なぬけ殻をすぺて集める。この間に採取数が100個以上になった場合は採取終了とする。採取数が100個未満の場合は、
- 採取ぬけ殻数が100個に達するまで採取を続ける。ただし、
- 採取時間が1時間(調査者数が3名以上の切合は45分)に達すると、採取ぬけ殻数が100個に達しなくても採取を終了する。
採取後その場あるいは持ち帰り、ぬけ殼の種名と数の割合を調ぺる。調査票の記入大阪府(市境が描いてある)およぴ大阪市(区境が描いてある)の地図を1部送付する。調査地点に○と地点番号I〜wなどを記入し、調査票中に調査月日・調査地点名・環境(学校・公園・その他の別)・種ごとのぬけがら数・クマゼミ率(%)を記入する。
- <調査対象生物>調査対象となるセミの種類と環境指標性の概要は次のとおり。見分け方などくわしいことは別途配布する参考資料『セミのぬけがら調ぺ』を参照されたい。

- クマゼミ:透明な翅を黒光りする大型のセミで、南方系の種と言われる。幼虫は、温度が高く、乾燥した土壌に耐えるため、ヒートアイランド化が進む都市部ではほとんどのぬけがらがクマゼミとなる。全ぬけがらに占めるクマゼミのぬけがらの割合をクマゼミ率として、土壌の高温化・乾燥化の目安とすることができる。ただしこれは近畿地方中部など暖帯中部で適応できる指標であって、関東
�平野などで同様のことがいえるわけではない。
- アブラゼミ:翅は濃い茶色で、クマゼミよりやや小さい中型のセミ。都市部にも少なくないが、幼虫はクマゼミよりはやや温度が低く・湿り気を含む土壊で生息することが多い。クマゼミと共存する地域では、羽化も梅雨明け直前およぴ立秋以降の方が盛夏よりも多くなることがある。
- ミンミンゼミ:近畿中部では、平野部周辺の標高100〜300mていどの低山の森林で多く見られる。都市部でもまれにみられるが、ここ数年大阪市内では、ぬけがらは見つかっていない。いわゆる里山を代表する昆虫と言うことができる。成虫はからだに緑色の縁取りが見られるので容易に区別できるが、ぬけがらがアプラゼミと似て識別は難しい、同定に自信がなけれぱ、フィルムケースなどに採取して幹事校まで送付いただきたい。
- ニイニイゼミ:都市部にも周辺の里山にも見られる種類。小型種で、ぬけがらは全身泥をかぶっているので容易に他種と区別できる。環境指標性は不明だが、極端な土壌乾燥では生育できないようである。
- ツクツクボウシ:成虫はふつう立秋以後に出現する(一部7月下旬から見られる)。雄は(夏が終わるのが)「つくづくおしい」と鳴くと聞きなすためこの名が付いた。都市公園にも標高500m程度の山地にも出現するので、温度や乾燥に対する適応能力は高いが、土壌の極端な高温・乾燥には耐えられない。
- ヒグラシ:成虫は「カナカナカナ」という哀調のある声で鳴く。曇天やタ刻近くに鳴くことが多いため「日暮らし」の名が付いた。比較的山地性のセミで、大阪付近では標高300mを越えないと出現することは少ない、しかし、成虫は飛翔によって都市部でも見つかることがある。環境指標性は不明だが、土壌の高温・乾燥には弱いようである。
調査緒果調査結果は8月末までに府立泉南高校の田中正視(メールコース⑬)まで送付してください。なお、府のメールが使用できない学校では、教育大附属高校池田の中井一郎(〒563−0026池田市緑丘1−5−1)まで郵送してください。結果をまとめた報告書は99年春に作成して、調査協力校にフィードバックする予定です、また、その一部は研究会50周年記念会誌などで発表し、、府下全校に配布されます。指標生物調査委員会昆虫班委員:田中(泉南)、北浦(美木多)寺岡(市岡)、中井(附池田)