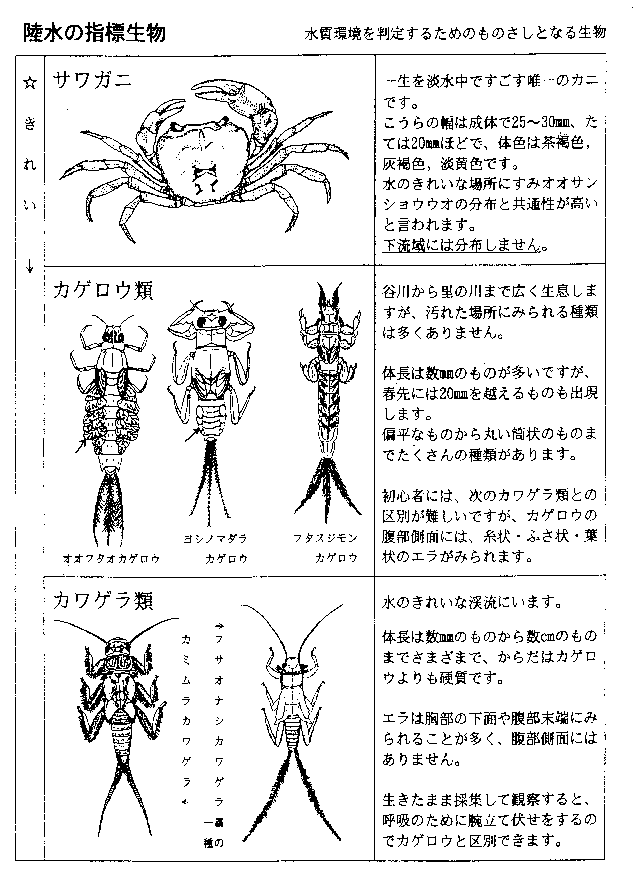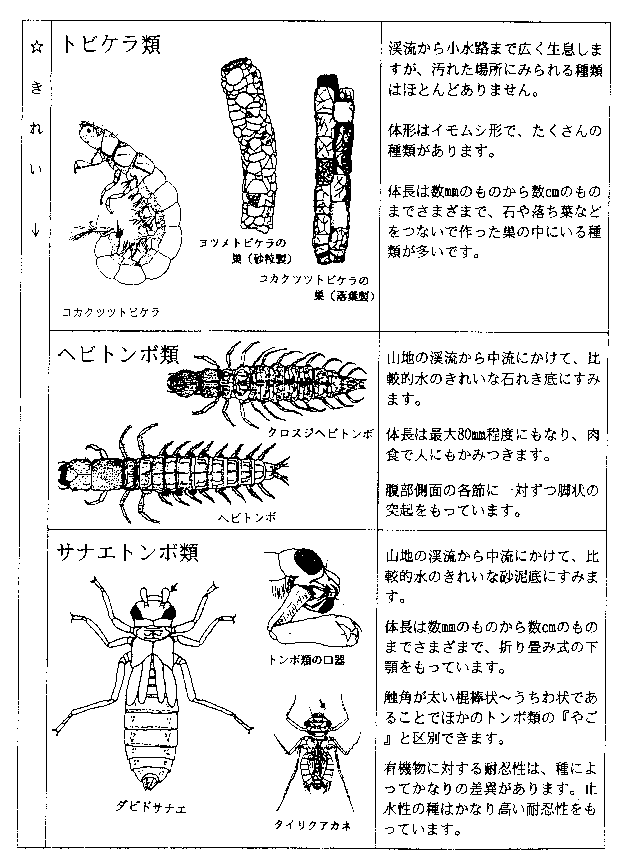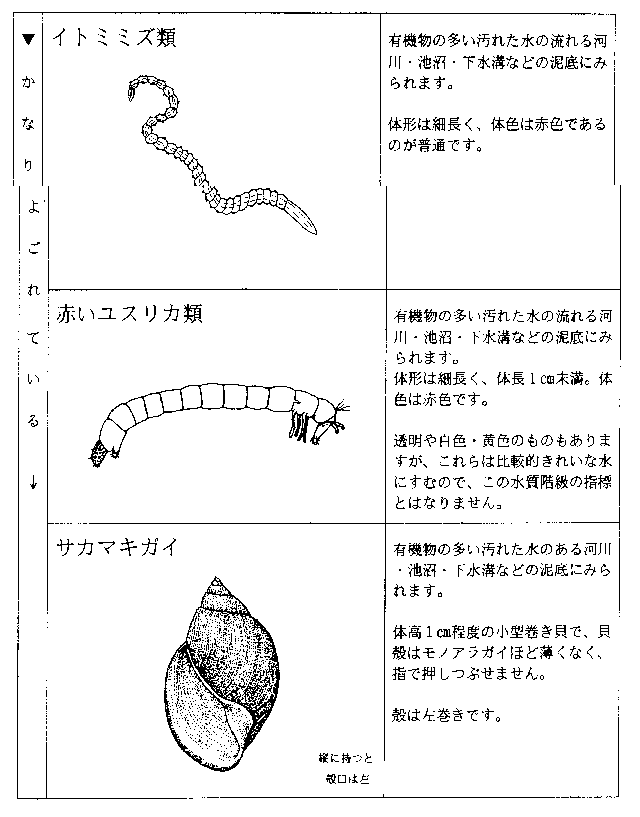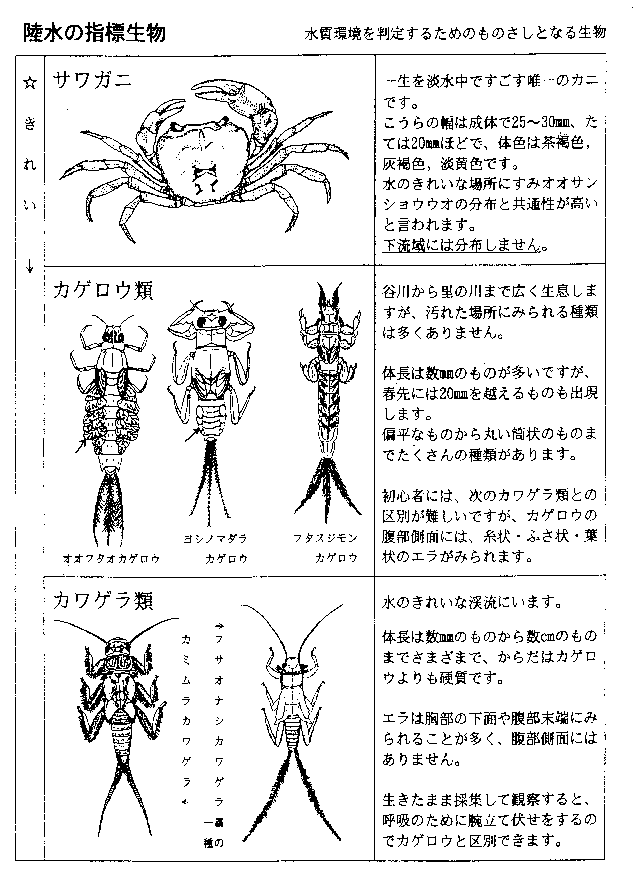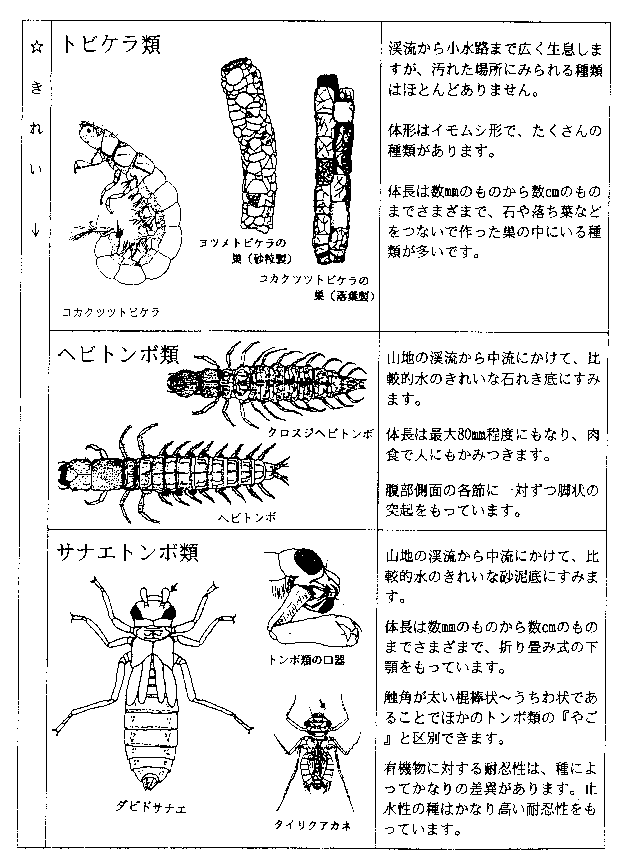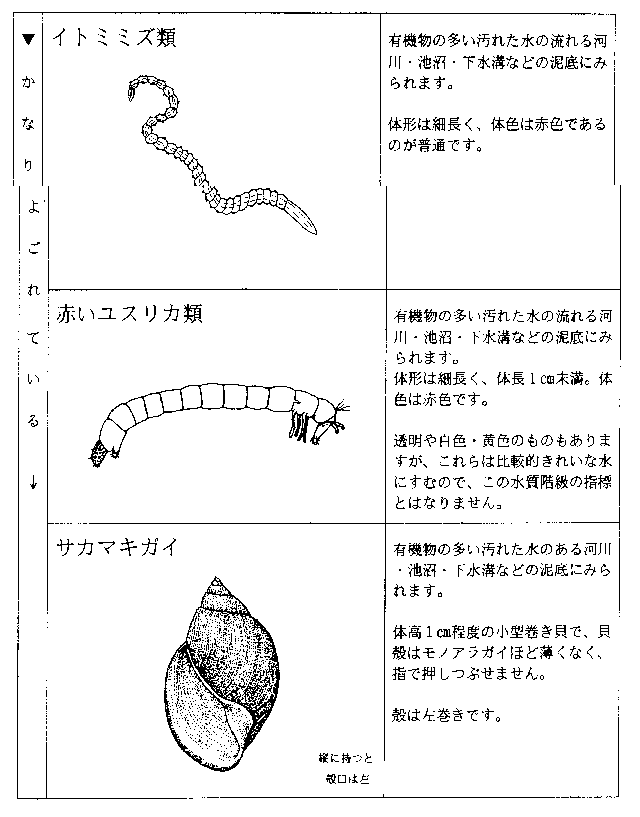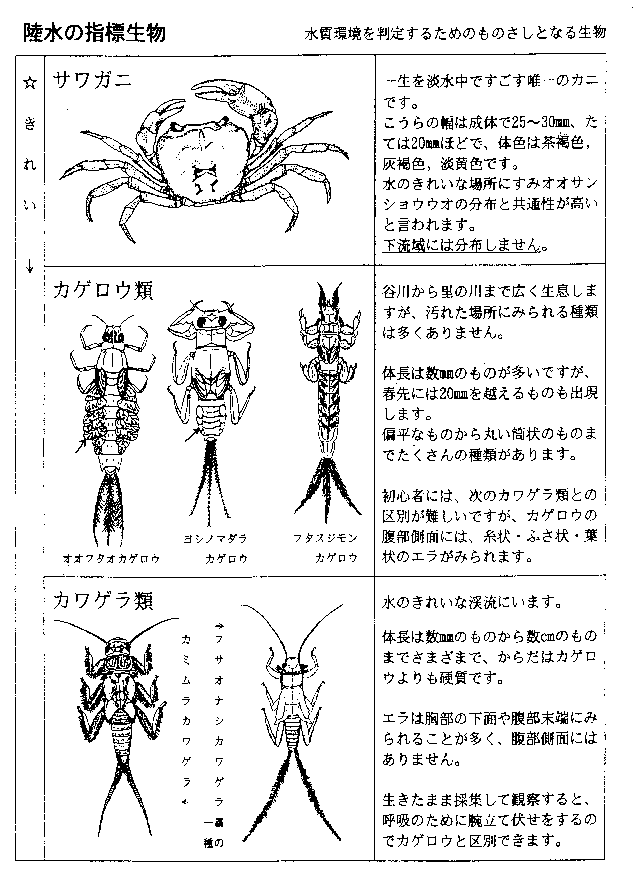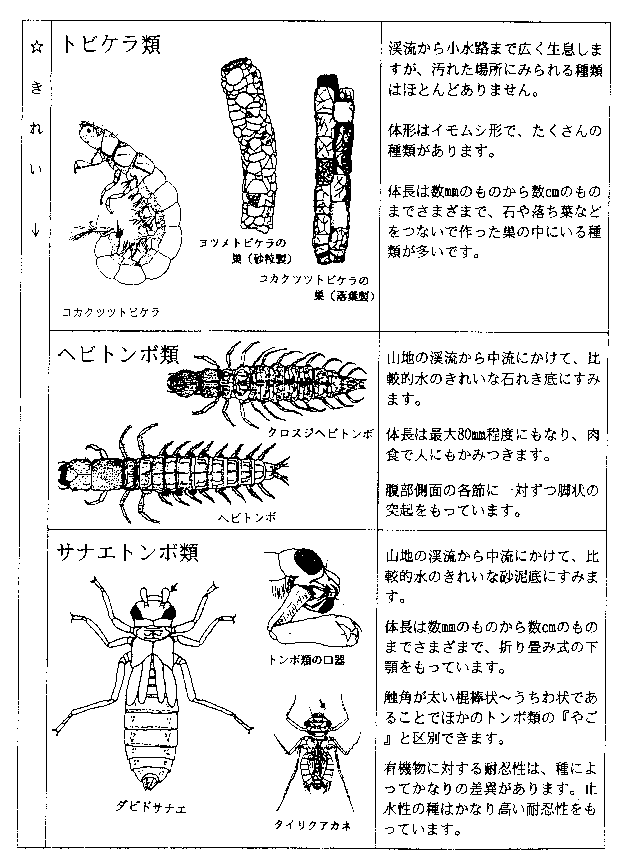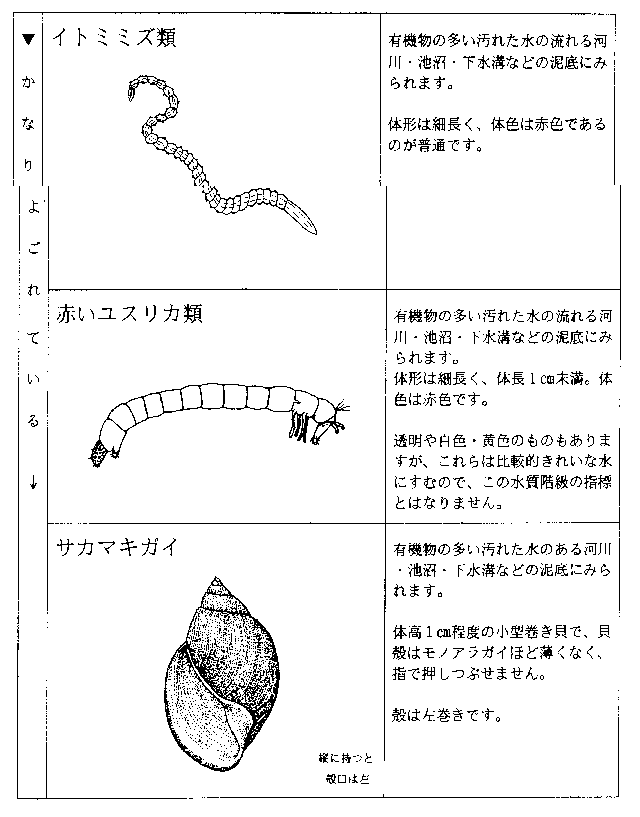大阪府高等学校生物教育研究会
河川の水生生物調査実施要領
- <実施方法>大阪府の主な河川について、高校の生物部あるいは生物科教職員の手で、環境指標となる代表的な水生生物の存否を確認する。また、パックテストによって、簡便法ながら、化学的水質調査も同時に行う。
- 1校の生物部あるいは教職員(教職員グループも可)に原則として1つの河川の調査を依頼する(希望によっては複数の河川の調査を担当することもできる)。
- 1つの河川の上流から下流にかけて、6地点程度を選ぴ、調査地点とする(少なくとも3地点程度は実際に河川敷に降りて生物調査ができるところを含むようにする)。
- 各調査地点で、下記の10種類の生物種・生物群が生息するかどうかを確認する。存否の確認方法は生物ごとに決める。
- 各調査地点で、生物調査と同時にパックテストによる簡易水質調査を行う、調査項目はCOD、アンモニア態窒素、リン酸態リンであり、これらはいずれも有機汚濁の指標となる、協力校には各調査キットを5地点分ずつ配布する。不足分は各校で購入いただきたい、なお、水質環境指標として優れていると言われる亜硝酸態窒素についても調査したい、各校でパックテストを購入いただき、調査結果をご報告いただけれぱ幸いである。
- 河川地図への書き込みについて
大阪府河川地図兼調査表を1部送付する。2枚以上必要ならコピーして使用する、河川地図には、調査地点に○(河川に入れないような環境であれぱ●)と地点番号I~wなどを記入し、調査表に調査年月日・調査河川名・調査地点・生物の存否(各種ごとに存在する種は○を、存在が磯認できなかった種は×)・水質調査結果を記入する。
- 調査時期:夏休み中の適当な時期とする、できれぱ8月上旬~中旬が望ましい。なるぺく雨天の日およぴ雨天の日の翌日は避ける。1っの水系はできるかぎり1日のうちに調査する。
- <調査生物>調査生物種・生物群10種の環境指標性の概要は次のとおり、見分け方も含めて、くわしくは別途配布する『指標生物ガイド』や研究会発行の『生物実習書』およぴその解説書の河川の環境調査の項を参照されたい。
- サワガニ:きれいな水か流れる河川の指標生物。オオサンショウウオなどの行動範囲とも分布状況が共通することが多い。
- カゲロウ・カワゲラ類:種によって環境指標性が異なるが、多くの種はきれいな水が流れる河川の指標生物。種の同定は熟練を要し、カゲロウとカワゲラの判別も初心者には容易ではないが、ほかの生物群との識別は困難ではない。
- トビケラ類:種によって環境指標性に違いがあるが、多くの種はきれいな水が流れる河川の指標生物となる。種の同定は難しいものの、イモムシ型の動物は水中には少ないので、ほかの生物群との識別は容易である。いろいろな形の種特有の巣をもつものが多い。
- ヘビトンボ類:比較的きれいな水が流れる河川の指標生物、水生昆虫の中では同定が容易で、水生生物群集が豊富な環境にのみ生息する。
- カワニナ類:比較的きれいな水が流れる河川の指標となるが、種によってはやや汚れた水にすむものもある。同定は平易でないが、ほかの生物群との識別は容易。
- ミズムシ:やや汚れた水が流れる河川の指標生物。オカダンゴムシ(いわゆるマルムシ)と近縁で、同定は容易。
- ヒル類:やや汚れた水が流れる河川の指標生物。細かな同定は難しいが、ほかの生物群との識別は容易。赤色がかった色調の種類は有機物の豊富な環境に生息する。
- サカマキガイ:かなり汚れた水が流れる河川の指標生物。ほかの貝類とは巻き方が逆(左巻き)なので、識別は容易、有機物の量富な環境に生息する。
- イトミミズ類:かなり汚れた水が流れる河川の指標生物。細かな同定は難しいが、ほかの生物群との識別は容易で、有機物が極めて豊富な環境に生息する。
- 赤いユスリカ類:かなり汚れた河川の指標生物、細かい同定は難しいが、ほかの生物群との識別は容易。濃い赤色の幼虫は、有機物が極めて豊富で酸素の欠乏しがちな環境にすみ、アカムシとよばれる。
- <生物の確認方法>A.①・②・③・④・⑧・⑨については、タモ網やザルなどを河川の石礫底の下流側にかまえて、上流側の石礫を足などを使って動かして、網の中に入った生物を謁ぺて確認する。B.③・④・⑤・⑥・⑦・⑩については、上記の方法を砂泥底でも行う。
- <簡易水質検査>調査対象水質項目の環境指標性の概要は次の通り。検査方法の詳細などについては、『指標生物ガイド』を参照されたい。
- COD(化学的酸素要求量):水質汚濁を起こす有機物には、家庭や工場などから排出される有機物をはじめとする還元性物質が多い。酸化剤である過マンガン酸カリウムの消費量を求めることで、有機物による水質汚濁の指標としたものである。
- アンモニア態窒素:家慶排水を中心とする下水や農業排水には、アンモニア態窒素が多い。溶存酸素の存在下で微生物によって亜硝酸態窒素や硝酸態窒素となるが、汚染源近くや水中の酸素が少ないところでは、この値が大きくなる。
- リン酸態リン:リンは窒素とともにプランクトンや付着藻類の栄養源となって、水の富栄養化をまねく。特にリン酸態リンは生物に吸収されやすく、有機汚濁の原因となりやすい。家庭排水や農業排水の流入するところでは、大きな値になる。
- ☆亜硝酸態窒素:家庭排水や農業排水には、アンモニア態窒素が多い。しかし、アンモニア態窒素は、溶存酸素の存在下で微生物によって、比較的速く亜硝酸態窒素となる。亜硝酸態窒素は、硝酸菌など特定の微生物に利用される以外は比較的長く水中にとどまるため、アンモニア態窒素よりも水質汚濁指標としては優れていると言われる。
調査結果は9月5目(土)までに府立枚方淳田高校の坂井(メールコース⑤)まで送付してください。なお、府のメールが使用できない学校では、教育大附属高校池田の中井一郎(〒563-0026池田市緑丘1-5-1)まで郵送してください、指標生物調査委員会陸生生物班委員:安井(島本)、岡本(桃谷)、永井(清教)、橘(天王寺)坂井(枚方津田)、丹賀(大和川)、中井(附池田)