平成16年12月5日(日)更新
大阪府高等学校生物教育研究会
日本生物教育会全国大会(大阪大会)のページ
日本生物教育会(JABE)第60回全国大会
大 阪 大 会 の ご 案 内
第60回全国大会実行委員長 牧野 修司 (大阪府立刀根山養護学校長)
同 大会事務局長 木村 進(大阪府立泉北高等学校,生物科)
| 1985年の第40回大会以来、20年ぶりに第60回の記念すべき全国大会を大阪で開催いたします。前回は約600名の参加を得て、盛大な大会が開催されましたが、今回もこれまでの生物教育研究の蓄積を生かして、大阪らしい独創性のある充実した大会を目指して準備を進めております。現在までに、下記のように大会の概要が決定したしましたので、皆さんにご報告させていただきます。ただし、なにぶん来年夏のことであり、今後諸般の事情によって変更になる項目もありえますので、ご了解ください。皆様におかれましては、ぜひとも2005年8月3~5日に行われる全国大会へ参加していただきますよう、お願い申し上げます。 |
記
1.大会主題 「ほんまにわかる生物教育の実践」
2.主 催 日本生物教育会・大阪府高等学校生物教育研究会
3.後 援 文部科学省・環境省・農林水産省・大阪府・大阪府教育委員会・大阪市
・大阪市教育委員会・大阪府私立中学校高等学校連合会・大阪府中学校理科教育研究会
・大阪市立中学校教育研究会理科部・大阪府小学校理科教育研究会
・大阪市立小学校教育研究会理科部・その他(現在申請中・申請予定を含む)
4.開催期日 2005(平成17)年8月3日(水)~5日(金)、理事会:2日(火)
5.大会会場 興国高等学校(JR環状線「寺田町」下車、徒歩約7分)
*現地研修・実験講習会は主に大阪府内の各地域や教育センター・大学・研究所などで実施。
6.日程の概略
|
| 日(曜) | 午 前 | 午 後 | 備 考 | | 2日(火) | (大会準備) | 全国理事会 (大会準備) | | | 3日(水) | 開会式・総会・記念講演 | 研究発表(口頭・ポスター) | 夕刻~懇親会 | | 4日(木) | 研究協議・閉会式 | 現地研修・施設見学・実験講習会KA | | 5日(金) | 実験講習会KB(終日)・現地研修(前日より継続) | |
|
*現地研修は4日~5日の1泊2日、施設見学会は4日午後半日、
*実験講習会KAは4日午後半日コース、KBは5日一日コースを予定。
7.記念講演 「生きものとしての人間を実感する生物教育」 講師:JT生命誌研究館 館長 中村桂子氏
「現代生物学はDNA(ゲノム)を通して地球上のすべての生物は祖先を一つにする
仲間であることを明らかにしました。人間もその中の一つです。生物教育が、自分自身
生きものであることを実感させるものであってほしいと思います。“生命誌”という
新しい切り口で具体的に何ができるかをお話しします。」(中村桂子氏談)
生物教育の中で、生徒達が「いのち」について知識として知るだけでなく、「ほんまに
いのちを大切にせなあかん」と心から感じてくれるには、どうすればよいのだろうか。
生命誌研究館で最新の生物研究を一般市民に分かり易く伝える実践を続けてこられた
先生に、最近のいのちをめぐる様々な話題を織り交ぜながらお話ししていただく。
《講師紹介》東京都出身。1936年生。東京大学理学部化学科卒。三菱化成生命科学研究所
・早稲田大学人間科学部教授、大阪大学連携大学院教授などを歴任。著書・訳書多数。
*研究協議の4つの分科会の講師の方にそれぞれのテーマに沿った講演をしていただく予定。
8.研究発表(口頭発表とポスター発表の2部門)
① 教材研究・実験観察に関するもの
② 環境教育・自然観察に関するもの
③ その他(学術的研究・教育課程・教育メディアなど)に関するもの
9.展示部門
① 高校生(生物部など)の研究発表展示(ポスター発表:賞状授与)
② 日本生物教育会各都道府県支部・生物教育関係業者展示(ブース提供)
③ その他(大阪の自然や生物教材に関する展示などを検討中)
10.研究協議(4つの分科会形式で実施。講師の基調講演・話題提供者の発表・研究協議)
①「高校生物の次期教育課程について考える」(講師:文部科学省教科調査官 田代直幸氏)
*講師から検討が始まっている次期教育課程について報告をいただき、高校の生物教育の
現場の様々な意見を交換して、ぜひとも、まとまった形での提言を行いたい。
②「生物の授業の中で命をどう扱うか」(講師:近畿大学先端技術総合研究所 加藤博己氏)
*講師から生命工学の最先端の話題と問題点を紹介していただき、生命倫理に関する学校
での授業実践の話題提供を受けて、授業で「いのち」をどう扱うべきか協議したい。
③「実験実習の現状と今後のあり方」(講師:大阪府教育センター 江坂高志氏)
*探究活動や課題研究が導入されて約10年。各地から実験実習の現状の報告を受け、
教育現場や生徒が変化している中で、実験実習の今後の在るべき姿について協議したい。
④「子どもたちをいかに自然に親しませるか-小中高連携をはかる」(講師:滋賀県立琵琶湖博物館 布谷知夫氏)
*環境教育の重要性が叫ばれ、様々な実践も行われているが、子ども達の自然離れは
止まっていない。講師を含めた4人の報告を受け、どう働きかければよいかを考えたい。
11.現地研修(GCは4~5日の1泊2日、GBは5日日帰り)
日本の南限域にある太平洋型ブナ林(天然記念物指定)の生態と保全活動に関する
研修を中心に、ブナ林の鳥類の観察や、平地の照葉樹林(コジイ林)の観察などを行なう。
ナショナルトラスト運動発祥の地である和歌山県田辺市の天神崎で、岩礁生物の観察を
中心に実施。地元の保全活動や小学校や高校での臨海実習の報告を受けて研修を深める。
大都市周辺に残る貴重な淀川の下流域(十三干潟から城北公園)の自然を、魚類などの
大会2日目の午後後半の日程で、大阪の代表的な生物教育施設を訪れ、それぞれの施設の
担当者から説明を受けながら見学するとともに、現場での活用について考えたい。
SA-1:JT生命誌研究館 SA-2:海遊館 SA-3:天王寺動物園 SA-4:雑魚寝館
13.実験講習会(KA:8月4日午後、または、KB:8月5日終日)…テーマは仮題
② (KB-2)「進化する視物質遺伝子を見よう(仮題)」大阪大学理学部 久冨 修氏
④ (KB-4)「タンポポ調査と雑種タンポポの解析(仮題)」大阪市立大学理学部 伊東 明氏
⑤ (KB-5)「体外受精」近畿大学生物理工学部 細井 美彦氏
⑥ (KB-6)「植物の進化について(仮題)」大阪市立自然史博物館 岡本素治氏
⑦ (KB-7)「バイテクキットを用いた実験講習会」大阪教育大学 片桐昌直氏
⑧ (KB-8)「環境化学物質などの遺伝子影響(検討中)」大阪府立大学先端科学研究所 八木孝司氏
⑨ (KA-9)「オサムシの系統解析」滋賀県立琵琶湖博物館 八尋克郎氏
⑩ (KA-10)「光学顕微鏡の使用法」オリンパス大阪 テクノラボ 白鳥 敏夫氏
⑪ (KA-11)「レリーフモデル作製講座」大阪府立生野高校 北浦 隆生氏
14.記念出版物
・ 大会記念誌「生物作業教材集」
15.大阪大会事務局(連絡先):大阪府立泉北高等学校 生物科 木村 進
〒590―0116 大阪府堺市若松台3-2-2 または電子メール「
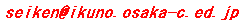
」へ
このホームページに関するご意見、ご感想は
E-mail: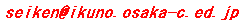 までお願いします。
までお願いします。
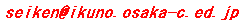 」へ
」へ
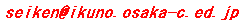 までお願いします。
までお願いします。