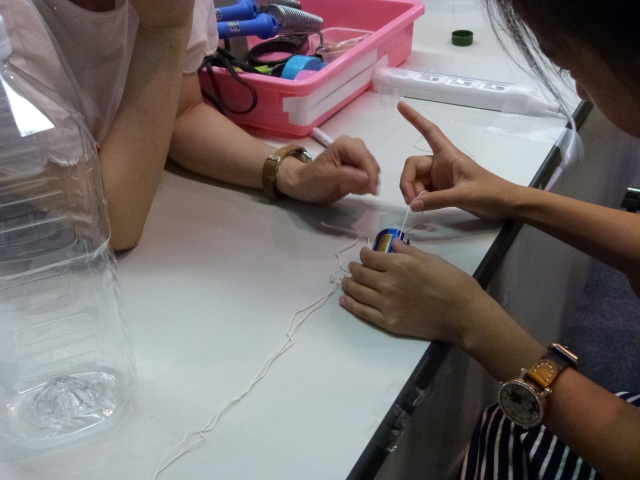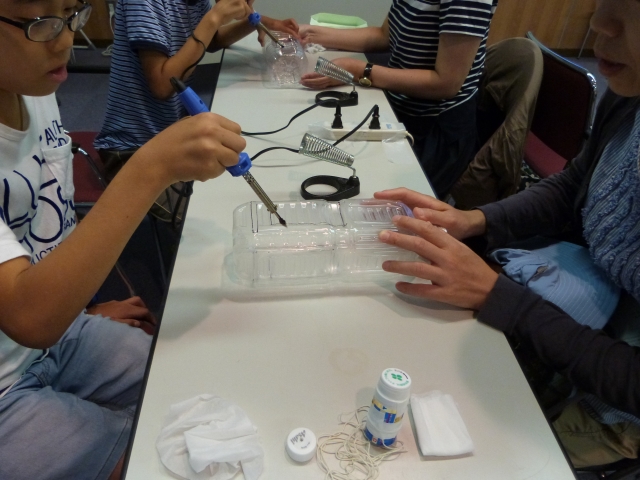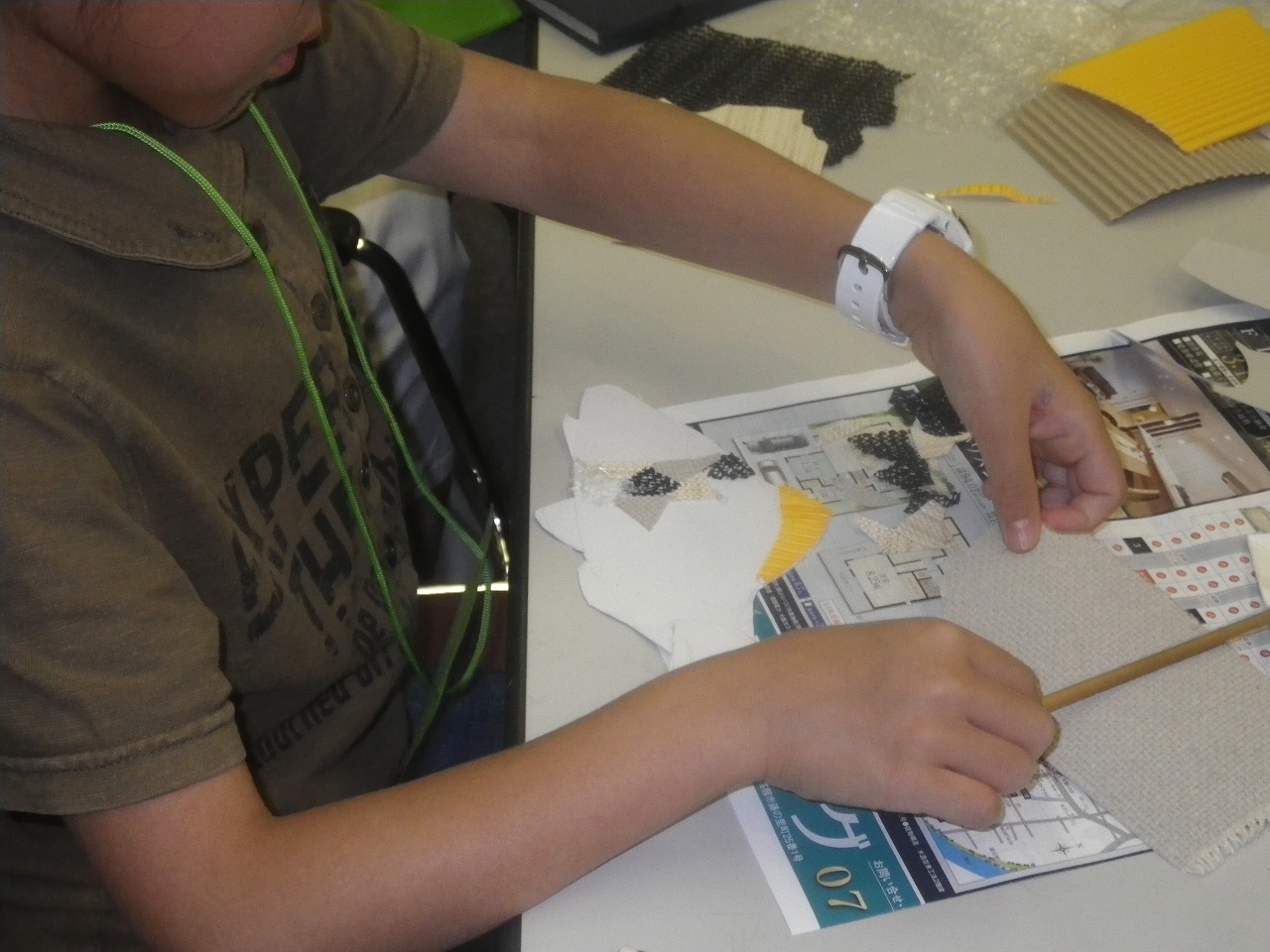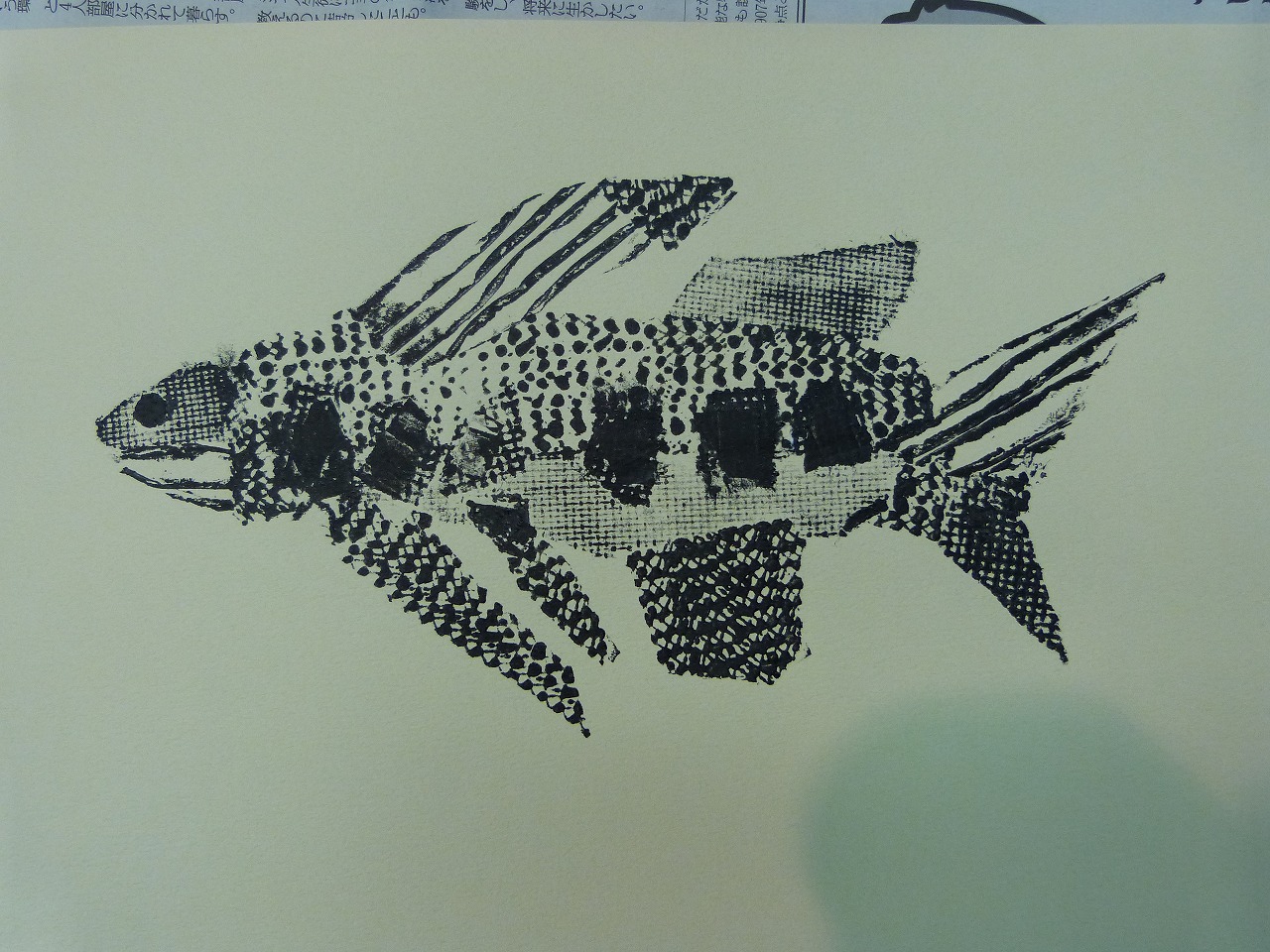第6回ハグロトンボしらべ隊調査会報告&次回予告【9月4日】
2016年08月27日
今日は川グループと陸グループに分かれ調査をした。子どもが少なくなってきておとなのハグロトンボが増えている。今日は暑かったから日かげにたくさんいた。どんどん川にトンボが増えてきた。なわばり争いをしているトンボがいっぱいいた。トンボをつかまえてみると、羽がぼろぼろになっているのがいた。再ほかくのトンボも増えてきた。午前は310頭とれた。
午後は西山川と、にしのかわらばしからしょうおんじばしと、しょうおんじばしからすいどうばしの3つのグループに分かれた。西山川は再ほかくがいなかった。にしのかわらばしからしょうおんじばしはしょうおんじばしの近くにたくさんいた。しょうおんじばしからすいどうばしは水辺の木かげに成じゅくしきれていないトンボがけっこういた。
午後は141頭とれて、合計は451頭になった。毎年いっぱいとれたあと、トンボの数が減る日がある。その日かもしれないし、いつもたくさんとる人が休んだためなのか、さてどちらでしょう。(隊員 R.F)
今回は水辺でたくさん捕獲することができました。ハグロトンボの行動も活発になり、なかなか簡単に捕まえられないことも。。暑い日だったので、水辺近くの木かげも人気スポットでした。
今年の調査はピークに達したようですね。9月はどのような動きになるでしょうか。
次回の調査会は9月4日(日)10時~12時 川に入れる恰好、暑さ対策、虫網を持って、
あくあぴあ芥川1階水上ステージ前に集合してください。
まだまだたくさん捕れると思います。初めての方もどんどん参加くださいね。




午後は西山川と、にしのかわらばしからしょうおんじばしと、しょうおんじばしからすいどうばしの3つのグループに分かれた。西山川は再ほかくがいなかった。にしのかわらばしからしょうおんじばしはしょうおんじばしの近くにたくさんいた。しょうおんじばしからすいどうばしは水辺の木かげに成じゅくしきれていないトンボがけっこういた。
午後は141頭とれて、合計は451頭になった。毎年いっぱいとれたあと、トンボの数が減る日がある。その日かもしれないし、いつもたくさんとる人が休んだためなのか、さてどちらでしょう。(隊員 R.F)
今回は水辺でたくさん捕獲することができました。ハグロトンボの行動も活発になり、なかなか簡単に捕まえられないことも。。暑い日だったので、水辺近くの木かげも人気スポットでした。
今年の調査はピークに達したようですね。9月はどのような動きになるでしょうか。
次回の調査会は9月4日(日)10時~12時 川に入れる恰好、暑さ対策、虫網を持って、
あくあぴあ芥川1階水上ステージ前に集合してください。
まだまだたくさん捕れると思います。初めての方もどんどん参加くださいね。




日時
2016年8月21日(土)10:00~15:00
場所
あくあぴあの近くの芥川と周辺の林
参加費
無料
参加数
23名
対象
だれでも(小学3年生以下は保護者同伴)