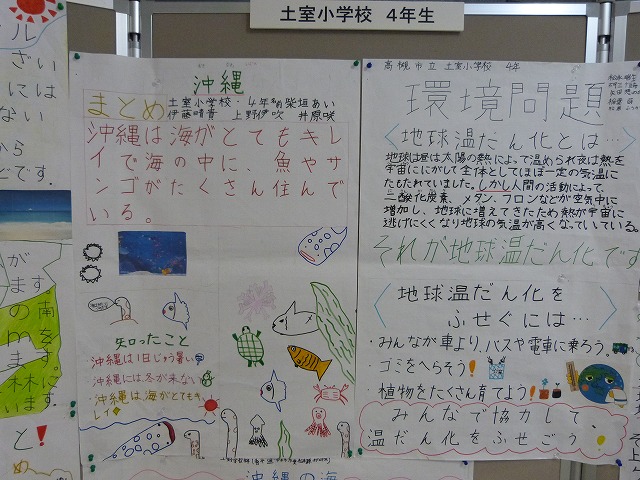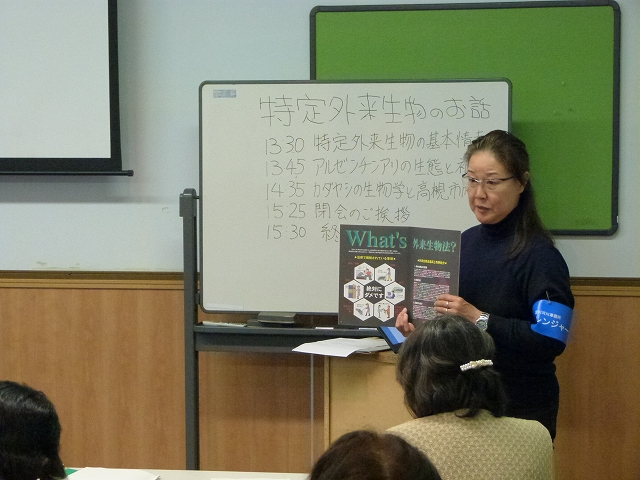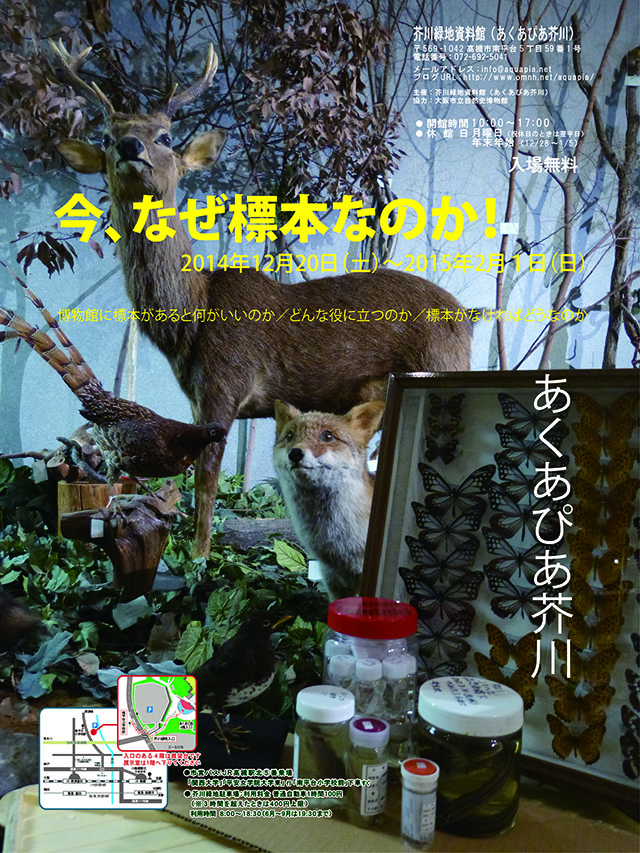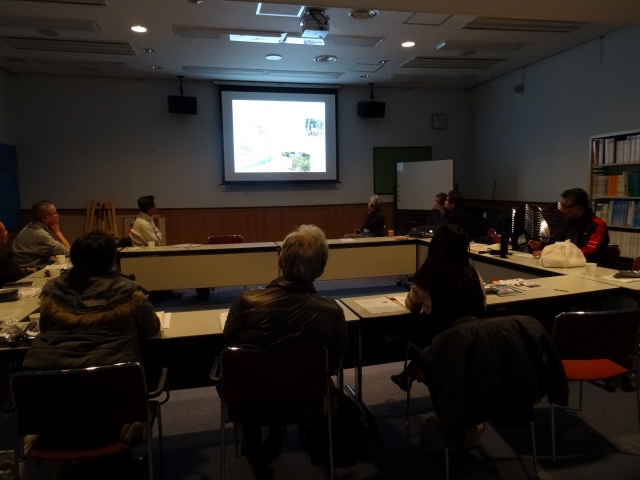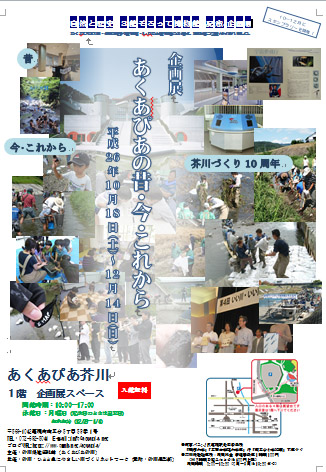【2月22日】自然観察会 「町なかのコケ」
2015年02月27日
雨あがりだったのでコケの葉が開き、絶好のコケ日和となりました。まずは西武百貨店の植え込みで、ゼニゴケ、ナミガタタチゴケなどを観察。伊勢寺への道すがら、ハリガネゴケ、ホソウリゴケ、ギンゴケが道路脇にぽこっと生えていました。伊勢寺ではサヤゴケ、ヒジキゴケ、エゾスナゴケ、ヤマトフデゴケ、ハイゴケ、タカネミゾゴケ、フクロヤバネゴケといった、たくさんの種類のコケが観察できました。毎年一番寒い季節に行う会ですが、今年は小雨でも暖かく、じっくりと観察することができ、地味で熱い観察会となりました。

植え込みの前で観察会

道路脇のホソウリゴケ

木の幹に生えるサヤゴケ

植え込みの前で観察会

道路脇のホソウリゴケ

木の幹に生えるサヤゴケ
日時
2015年2月22日(日)午後1時30分~午後3時30分
場所
JR高槻駅~伊勢寺
講師
道盛正樹氏(日本蘚苔類学会会員)
参加者
27名