自然観察会「高槻のナラ枯れ」

ナラ枯れの木を観察

一週間前に仕掛けたトラップ
たくさん入っていました

木を切ってみる

カシノナガキクイムシの孔道が見えます
 あくあぴあの理念(ミッション)はこちら
あくあぴあの理念(ミッション)はこちら
 |
 |
 |
 |
 |





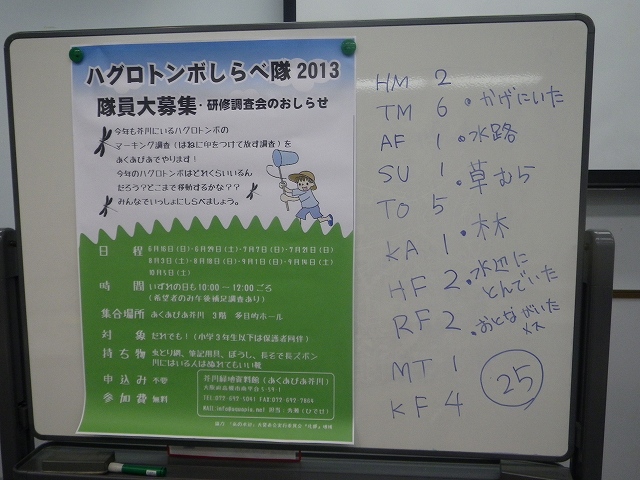





大阪市立自然史博物館で今年も11月10、11日に「大阪自然史フェスティバル2012」が開催されました。自然関連のサークル、地域の自然保護団体が活動を紹介し、交流するために行われるフェスティバルで、今年は100以上の団体が参加しました。初日は晴天で多くの人が来場されましたが、2日目は朝から雨。主催者は発表では1日目の来場者数が11,000人、2日目が6,000人でした。
あくあぴあ芥川は芥川倶楽部と共同での展示です。展示内容は、芥川倶楽部の活動紹介パネル(いい川WSパネル)及び今年の市民によるアユ遡上調査パネル、アユ遡上の動画(豊田さん撮影)、芥川の魚生体展示(17種)、あくあぴあ芥川で作成した冊子類、芥川の位置図などです。アユは捕れなかったので残念ながら展示できませんでした。魚の水槽とアユの遡上動画が人気がありました。配布物は、芥川倶楽部の季刊誌「あくたがわ水辺だよりNo.12,13」、魚と水生昆虫の下敷き、あくあぴあリーフレットなど。下敷きは魚を一生懸命見てくれた子どもに配布しました。
たくさんの人に芥川の魚を見ていただき、「アユが上ってきてるなんて知らなかった」と驚かれる方も。隣近所のブースはお魚関係が固まっていたので、いろんな会の人とも話をすることができました。

あくあぴあのブース

屋外会場の様子
日時:11月10,11日 午前9時30分~午後4時30分
場所:大阪市立自然史博物館



