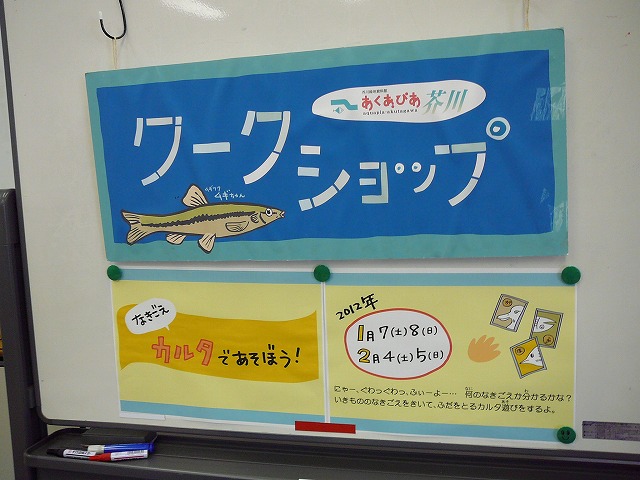あくあぴあリバーサイドコンサート
今年の5月3,4日も高槻ジャズストリートと一緒にコンサートを開催。あいにく二日目は雨でしたが、ジャズ界の大物シンガー!中本マリさんの時間は奇跡的に小雨になり、大勢のお客さんでにぎわいました。今年はジャズストバスが巡回していたのですが、時間によっては満席で乗れなかった方もいたようです。
あくあぴあ館内では子どもふれあい動物園、大水槽で魚のエサやり「もぐもぐタイム」なども大好評。公園の飲食ブースでは、あくあぴあ会場でしか食べられないブラックバスのフライやシカ肉ソーセージなども販売。昨年の台風で被災した和歌山県に向けて、はげましの連凧作りも行い、約50枚の凧が虹を背景に空を舞いました。


中本マリさんの歌声は4階まで響いていました。朝から雨が降り続いていたのに、この時には奇跡的に小雨に。最後には虹も出て、大勢のお客さんに楽しんでもらえました。


毎年あくあぴあから公演をお願いしてる上方太鼓連。ファンがついているようで、今年もたくさんのお客さんでにぎわいました。昨年は芥川にアユが上ってきたことから「若鮎」という新曲を披露。「太鼓を叩いてみよう」とお客さんに呼びかけた曲では、楽しくみんなで演奏させてもらいました。

楽隊ブラスレンジャーズ

田中暁

交野ジャズクリエーション

楽団よろづや

GrovalParadice

チョップコーンファミリー


WhiteCats


飲食ブースではあくあぴあ会場ならではのブラックバスのフライやシカ肉ソーセージを販売。ヤキソバ、綿菓子、かき氷もあります。


手作りサーターアンダギー、朝市の野菜も毎年好評で昼過ぎには完売。

ゴミはエコブースで分別


和歌山の被災地へむけたメッセージをつづった連凧をみんなで作りました。雨で大変でしたが、88枚の凧が完成。虹をバックに50枚が空を舞いました。


館内では。
普段は触ることのできない大きなニシキヘビやリクガメなどをさわれる動物園が大人気。
1日目の演奏後「もぐもぐタイム」では大水槽の魚がどうやってエサを食べるかを観察しました。