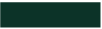






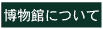
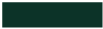
What's New
大阪市立自然史博物館の新着情報
« 2008年03月 | メイン | 2008年05月 »
丹波竜は、2006年兵庫県丹波市で発見された草食恐竜で、国内で見つかった恐竜化石としては、最大級とされています。
特別展「ようこそ恐竜ラボへ!」では、この丹波竜の標本3点(しっぽの骨など)を展示し、またパネルや映像で発掘の様子を紹介しています。丹波竜に関する展示は、5月18日(日)までです。
5月18日に行われる恐竜・ラボトークでは、兵庫県人と自然の博物館の三枝春生研究員による、丹波竜の発掘に関する最新報告を聞くことができます。
恐竜・ラボトークについての詳しい情報は、博物館のイベント情報をご覧ください。その他にも、さまざまなイベントを開催しています。
博物館イベント情報
丹波竜に関する詳しい情報は、丹波竜.comをご覧ください。
投稿者: 日時: 19:23 | この記事のみ表示
大阪市立自然史博物館では、月に1度の土日、子どもたちや親子連れのみなさんに展示を楽しんでもらうために、子どもワークショップや探検クイズを実施しています。ワークショップでは展示を眺めながら工作をしたり、絵を描いたり、ハカセ(博物館の学芸員)とお話をしたり、2008年度は7種類・計35日程度のプログラムを予定しています。探検クイズでは、子どもたちに常設展示をより楽しんでもらえるよう、主に土曜日、日曜日にスタッフが遊び方のお話をしています。
今回、スタッフや学芸員と一緒に、このワークショップやクイズの運営補助をしていただく学生ボランティア「子どもワークショップ・サポートスタッフ」を大募集します。子どもが展示と出会った時の様々な反応に共感できる方、むむ、ちょっと面白そう、おお、ちょっとやってみたい、と思った方、ぜひチャレンジしてください!
なお、本募集は3月末でいったん締め切りましたが、定員に余裕がありますので、二次募集を行うものです。
対象:18歳以上の学生で、週末のプログラムに2ヶ月に1回程度参加できる方。
期間:2008年4月から2009年3月まで(年間登録制)
募集人数:15〜20名程度
応募方法:往復はがきまたはメールに住所、氏名、学校名、学年、電話番号、メールアドレスを明記して、4月23日(水)までに届くよう、自然史博物館「ワークショップサポートスタッフ係」(メールはgyouji@mus-nh.city.osaka.jp)まで申し込んでください。研修を4月29日(火・祝)午前10時15分〜午後5時に行います(二次募集では、この研修への参加を必須とします)。研修と活動の詳細は返信でお知らせします。
その他:サポートスタッフとしての参加には規定の交通費を支給します。
申込み・問合せ先:
〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-23 大阪市立自然史博物館
「ワークショップサポートスタッフ係」
tel: 06-6697-6221 / e-mail:gyouji@mus-nh.city.osaka.jp(担当:石田・和田・中条・釋・中原)
博物館の概要、アクセス、過去のワークショップなどはこちらをご覧下さい。
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 16:25 | この記事のみ表示
大阪市では、平成20年5月18日(日)の「国際博物館の日」を記念して、市民の皆様とともにこれからの博物館・美術館のあり方について考えるシンポジウム「都市の魅力発信と博物館連携-大阪市の博物館を語る-」を開催します。自然史博物館も本事業に共催し、参画しています。
どうぞご参加ください。
大阪市では、他都市に先駆け、昭和の早い時期からさまざまなジャンルの博物館・美術館を順次設置し、その充実を図ることで一都市としては傑出した「博物館群」を築き上げてきました。また、各館では、資料の収集や展示だけでなく、市民が参画できる講習会や現地踏査、調査研究、友の会やボランティア活動などのさまざまな取り組みを行うとともに、最近では、これらの館が蓄積してきた館蔵品や知識・経験を基礎として、相互の連携を図ることで新たな魅力を創出し、学習や交流の拠点となることをめざしています。
このシンポジウムでは、前半の第1部で、大阪市の「博物館群」の沿革を振り返り、現状の取り組みをご紹介するとともに、現場の学芸員がそれぞれの館の魅力と活動状況をレポートします。後半の第2部では、各分野でご活躍されている方々から、博物館・美術館についてのさまざまなご意見をいただき、大都市における博物館群の魅力発信と相互連携のあり方についての検討を深めてまいります。これらを通じて、市民の皆様に、大阪市立の博物館・美術館に対するご理解をより一層深めていただく機会としたいと考えております。
記
1. 実施日時
平成20年5月18日(日) 10時30分~16時
2. 実施場所
大阪歴史博物館 4階 講堂
大阪市中央区大手前4-1-32
プログラムなど、詳細はこちらをご覧ください。
http://www.city.osaka.jp/yutoritomidori/report/culture/20080417.html
投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 23:08 | この記事のみ表示
現在好評開催中の「ようこそ恐竜ラボへ -化石の謎をときあかす-」に関連して、4月24日まで、大阪市役所玄関ホールで「モンゴル発掘写真展」を開催中です。
この写真展は、「ようこそ恐竜ラボへ-化石の謎をときあかす-」で展示されている恐竜化石を発掘した時の様子や、恐竜化石のレプリカを展示しています。「恐竜ラボ」展では展示しきれなかった写真やレプリカです。ぜひ、この写真展へも足を運んで下さい。大阪市役所玄関ホールで展示しています。
大阪市市役所は地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅下車、北へ200mほどです。市役所開庁時間内にご覧頂けます。
大阪市役所ホームページ
恐竜ラボ展特設ページ
なおこの写真展は,引き続き4月25日から6月1日まで,天保山マーケットプレイスで開催される「恐竜と海の生きもの2008」展の一部として,展示される予定です.
投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 17:40 | この記事のみ表示
5月10日(土)に、「地質の日」協賛行事として、第25回地球科学講演会「石油天然ガス資源をめぐる私たちの将来」を開催します。講師は石油探査の最前線で活躍しておられる、荒戸裕之氏(帝国石油(株)国内本部開発部部長)です。
私たちの暮らしに欠かすことのできない石油や天然ガスは、地質時代の生物遺骸が地下深部の地層中で姿を変えたものです。それが長い年月を経て地層中を少しずつ移動し、ある場所に集積すると、油田、ガス田が形成されます。人類はこの 100年間、幾多の油田、ガス田を発見し、それらを開発する技術を蓄え、採取した石油天然ガス資源を駆使して高度な文明社会を築き支えてきました。しかし、近い将来、石油天然ガス資源は枯渇する運命にあります。また、枯渇するまで今のように使い続ければ地球環境に大きな変化をもたらすことは必定です。石油天然ガス資源の成立と利用の実態を概観し、今私たちのおかれている立場について科学的に考えて見ましょう。
また、博物館のイベントページにも案内がありますので、ご覧下さい。
●特別行事 第25回地球科学講演会「石油天然ガス資源をめぐる私たちの将来」
私たちの暮らしに欠かすことのできない石油や天然ガスは、地質時代の生物遺骸が地下深部の地層中で姿を変えたものです。それが長い年月を経て地層中を少しずつ移動し、ある場所に集積すると、油田、ガス田が形成されます。人類はこの 100年間、幾多の油田、ガス田を発見し、それらを開発する技術を蓄え、採取した石油天然ガス資源を駆使して高度な文明社会を築き支えてきました。しかし、近い将来、石油天然ガス資源は枯渇する運命にあります。また、枯渇するまで今のように使い続ければ地球環境に大きな変化をもたらすことは必定です。石油天然ガス資源の成立と利用の実態を概観し、今私たちのおかれている立場について科学的に考えて見ましょう。なおこの講演会は「地質の日」協賛行事です。
日時:5月10日(土) 午後2時30分〜午後4時30分
場所:自然史博物館 講堂
その他:講演の手話通訳を希望される方は、4月22日(火)までに博物館(担当塚腰)へご連絡ください。
お問合せ:地史研究室の塚腰まで
お申込:申込みは不要です、直接集合場所・会場へお越しください
講師:荒戸裕之氏(帝国石油(株)国内本部開発部部長,石油地質学・シーケンス層序学)
参加費:無料(ただし、博物館入館料が必要)
共催:地学団体研究会大阪支部、日本地質学会近畿支部、日本堆積学会
後援:石油技術協会
投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 13:38 | この記事のみ表示
自然史博物館では、大型連休に伴い、4月28日(月)を開館いたします。4月22日(火)〜5月6日(火)は、休まず開館していますので、ゴールデンウィーク中いつでも自然史博物館をお楽しみいただけます。
5月7日(水)は休館日となりますので、ご注意ください。
開館時間は午前9時30分より午後5時00分、入館は午後4時30分までとなります。
現在開催中の特別展「ようこそ恐竜ラボへ!」に来場される場合は、午前中の早い時間帯が比較的混雑しておらず、おすすめです。
投稿者: 日時: 11:46 | この記事のみ表示

大阪市立自然史博物館では、平成20年4月26日(土)に第5展示室(第Ⅱ期、220㎡)がオープンします。「生き物のくらし」をテーマをとしてさらに掘り下げ、生き物の一生や生物の関係など、自然環境を読み解くための基礎となる生態学を楽しく紹介します。
展示の見どころは、ドングリの生死を分けるボールコースター、スマートボールで学ぶ島への移住シミュレーション、カケスのドングリ貯食ゲーム、シカとオオカミと植物の関係を題材にした人形劇などで、「生き物のくらし」をゲームや映像で学んでいただけます。
記者内覧会のご案内を含む、このプレスリリースの内容は、下記からダウンロードすることができます。
プレスリリース(PDF304KB)
展示室の詳細は以下に示します
新展示室の概要
名 称 第5展示室「生き物のくらし」
位 置 大阪市立自然史博物館 本館2階の一部
面 積 Ⅱ期220㎡(第Ⅰ期140㎡の工事と合わせて360㎡の展示室となります。)
テーマ 「生き物のくらし」
人も 虫も 鳥も 花も みんな つながって いっしょに生きている。私たちのまわりの生き物はどのようにくらしているのでしょう。そして私たちはどんなふうにつながっているのでしょう。
特 徴 生き物が環境や他の生物と影響を与えあう様子を人形劇や生態学的原理をもとにしたゲーム、映像など様々なしかけで楽しく紹介していきます。
展示コーナー
1.「種が違えば生き方も違う:生活史戦略」
ドングリなどを題材に、生活史戦略として生き物の増え方や生き延びる
工夫を紹介します。ドングリのボールコースターや、環境収容力シミュレーションゲームなどで楽しく学びます。
2.「果報は寝て待て」
休眠するカブトエビなどのふしぎな生活を、映像を交えて紹介します。
3.「新天地を求めて」
スマートボール型のゲームで生態学の基礎理論の一つ「島の生物地理学」を、水草のシミュレーションゲームでため池の植物の生活を理解してもらいます。
4.「食う、食われる:捕食-被食」
シカやオオカミを題材にした人形劇で自然の維持機構を紹介します。
5.「取り合う関係:競争」
同じ資源を取り合う生物同士の関係を、コンピューターと対戦して体験します。
6.「寄生と共生」
菌類と植物、動物と植物の間のいわゆる共生関係も微妙なバランスの上になり立つ関係であることをカケスのドングリ貯食ゲームなどで示します。
画像の確認
7.「三角関係:第3者を介した種間相互作用」
シカがササを食べ、さらにササの下から芽生える樹木の芽生えにも影響を与える。そんな生物同士の姿を実際の研究例に基づいて紹介します。
8.「生き物が生み出すすみ場所:すみ込み連鎖」
生物が他の生物の供給源になり、森の生物相はますます豊かになっていきます。
上記のうち、1-3は種ごとの生活史戦略を、4-6は生物間相互作用を主に扱う展示コーナーとなっています。これらをご覧頂くことで、昨春整備した第I期部分への理解もさらに高めることができると考えています。新展示によって博物館全体での相乗効果を発揮し、市民の皆様の自然への理解を深めることができれば、と考えています。
投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 14:00 | この記事のみ表示
●遠足の下見説明会について
自然史博物館では、遠足見学をより楽しく、スムーズにしてもらうために、下見説明会を開催しております。
説明しているのは、入館の手続き方法や経路、博物館からの学校遠足に関するお願い、簡単な博物館の見どころなどです。
日時:4月1日(火)〜4日(金)、4月8日(火)〜11日(金)の10時〜12時、13時〜16時半まで、30分ごとに開催しています。
(休館日以外、閉館時間までは、この他の日や時間も下見対応をしています。)
注意:下見でのご来館は、博物館事務室入口をご利用ください。
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/1attention/parkmap.html
●遠足下見説明会で、植物園を案内します
上記の下見説明会に合わせ、4月8日(火)〜11日(金)のそれぞれ15時から、植物研究室の学芸員による、長居植物園案内を実施します。春の草花や樹木の解説など、遠足時の長居植物園見学に参考になるお話が聞けます。何人かで下見に来られるときには、説明会に参加する方、植物園案内に参加する方と分かれて下見することもできます。
日時:4月8日(火)〜11日(金)15時〜16時
集合:自然史博物館 集会室
場所:長居植物園
定員:30名
申込み:不要。博物館事務室入口からお入り下さい。
投稿者: 日時: 13:28 | この記事のみ表示
検索
大阪市立自然史博物館
カテゴリー
- #おうちミュージアム (16)
- イベント情報 (151)
- テーマ展示・ミニ展示 (15)
- トリケラトプス展 (11)
- ホームページのお知らせ (20)
- 今月の自然史博物館 (9)
- 博物館からのお知らせ (447)
- ネイチャーホールの貸館イベント (2)
- 友の会からのお知らせ (13)
- 子どもワークショップ (10)
- 学校関係のみなさんへ (28)
- 書籍 (9)
- 特別展 (7)
- 2015年以前の特別展
- きのこのヒミツ (11)
- たまごとたね (10)
- のぞいてみようハチの世界 (8)
- ようこそ恐竜ラボへ! (9)
- スペイン奇跡の恐竜たち (12)
- ダーウィン展 (7)
- ホネホネ探検隊 (5)
- 世界のチョウと甲虫 (2)
- 世界一のセミ展/2007夏 (12)
- 世界最大の翼竜展 (5)
- 地震展2008 (12)
- 大化石展 (11)
- 大恐竜展 (13)
- 大阪湾展 (9)
- 新説・恐竜の成長 (13)
- 海はモンスターでいっぱい (7)
- 淀川展 (6)
- 発掘!モンゴル恐竜化石展 (9)
- 都市の自然 (8)
- きのこ!キノコ!木の子! (10)
- ノーベル賞受賞100年記念「アインシュタイン展」 (5)
- メガ恐竜展 (7)
- 大阪アンダーグラウンド (6)
- 大阪アンダーグラウンドRETURNS (1)
- 恐竜の卵 (5)
- 日本の鳥の巣と卵427 ~小海途銀次郎 鳥の巣コレクションのすべて~ (6)
- 氷河時代 (10)
- 瀬戸内海の自然を楽しむ (12)
- 特別展「大地のハンター展」 (4)
- 特別展「昆虫」 (9)
- 特別展「植物 地球を支える仲間たち」 (3)
- 特別展「毒」 (1)
- 生命大躍進 (10)
- 知るからはじめる外来生物 (7)
- 石は地球のワンダー (8)
- 2015年以前の特別展
- 特別陳列 (10)
- ヘルマン・ヘッセ昆虫展 (3)
- 深海生物の写真展 (2)
- 研究成果 (11)
- 自然史博物館YOUTUBE (8)
月別アーカイブ
最近のエントリー
Movable Type 3.2-ja-2
