昆虫の宝庫であった里山が変貌しています。種々の要因が里山の生き物に複合的に影響し、身近にいたはずの昆虫が徐々に姿を消しているのです。その実態をさぐる講演会を開催します。この講演会では、近年始まったばかりの京阪神地区のガの生息調査や、保全に向けての活動についてまず報告していただきます。そして、これまで総括的に紹介されることが少なかった紀伊半島のチョウ相やその変化、近畿地方におけるチョウの生息状況、および各府県において保全することが望まれる重要なチョウについての報告を受けます。また、身近なチョウやガの保全に関しての意見交換も行いたいと考えています。
日時:10月5日(日) 午後1時~午後5時
場所:大阪市立自然史博物館 講堂
主催:日本鱗翅学会近畿支部・大阪市立自然史博物館
内容:
1. 京阪神地区におけるガの現状(木下總一郎氏)
2. 紀伊半島のチョウの生息状況(奈良県:伊藤ふくお氏、和歌山県:諏訪隆司氏、三重県:中西元男氏)
3. 近畿地方のチョウの生息状況と保全が必要な種や地域(各府県の自然保護委員)
4. 総合討論
参加費:無料(ただし展示を見る場合には博物館入館料が必要)
その他:内容は当日一部変更になる場合もあります。
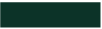






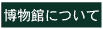
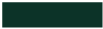
What's New
大阪市立自然史博物館の新着情報
« 2008年08月 | メイン | 2008年10月 »

大阪市立自然史博物館では、平成20年 10月25日(土)から12月7日(日)まで特別展「地震展2008」をします。
この特別展会期中に特別展記念講演会や起震車での地震体験など、地震にまつわる多彩な関連行事を行います。
特別展では、地震とは何か、どうして日本では地震が多いのかといった基本的なことがらから、大阪周辺の活断層の分布や動き、今後数十年のうちに起こる可能性が高い次の南海・東南海地震について、科学的にどこまでわかってきたのかを紹介します。
展示を見るだけでなく、関連行事に参加し体験することで、地震に関する最新の研究成果を知る機会、市民のみなさんの疑問や不安に答え、防災や減災についても考える機会としていきたいと考えています。
行事の概要は以下に示すほか、博物館ホームページのイベント欄、地震展のページ、以下のリンクに示したプレスリリースでご覧いただけます。またプレスリリースには10月24日(金)午前11時から、自然史博物館 本館 集会室で行いますプレス内覧会の情報もあわせてご覧いただけます。
プレスリリース(PDF525KB)
地震展ホームページ
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/tokuten/2008quake/
(写真の説明)
琵琶湖西岸断層帯のトレンチ写真 滋賀県高島市で実施された琵琶湖西岸断層帯・饗場野(あいばの)断層のトレンチにあらわれた地層のズレ。写真左下から右上のずり上がる逆断層が観察できる。(写真提供:高島市教育委員会)
1.特別展記念講演会
①「スロー地震とは何か 巨大地震予知の可能性をさぐる」 〈10月27日締切・申込必要〉
1995年兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)が起こったあと、日本国内には高精度・高密度の地震観測ネットワークが整備され、地震に関する基礎的研究が飛躍的に進んでいます。その中の大きなトピックが、南海トラフや日本海溝などのプレート境界型巨大地震が想定される場所での「スロー地震」の発見と、「アスペリティ」という概念の登場です。スロー地震と普通の地震は何が違うの? アスペリティって何? 地震予知をめざした研究の最前線の話を伺います。
日時:11月 2日(日)午後2時~午後4時
会場:自然史博物館 講堂 定員:250名
講師:川崎一朗氏(京都大学防災研究所・地震予知研究センター 教授)
②「地震考古学から21世紀の巨大地震を考える」 〈11月14日締切・申込必要〉
地震活動を考古学的手法を用いて研究する「地震考古学」を提唱し、文献に記述がない時期の南海地震を検証するなどして、南海地震が規則正しい周期で起こってきたことを明らかにしてきた、産業技術総合研究所の寒川さんをお招きし、講演会を開きます。「地震考古学」の立場で、活断層から発生する内陸地震や、「今世紀の南海地震」像について解説していただきます。
日時:11月29日(土)午後2時~午後4時
会場:自然史博物館 講堂 定員:250名
講師:寒川 旭氏(独立行政法人 産業技術総合研究所 招聘研究員)
2.自然史オープンセミナー
①「地震-1.日本列島のおいたちと地震」 〈申込不要〉
第1回目は地震展の概要と、その中で特に日本列島のおいたちと地震との関係について解説します。
日時:10月 4日(土) 午後3時~午後4時30分 場所:自然史博物館 集会室
講師:川端清司学芸員(地史研究室)
②「地震-2.大阪の地盤と地震」 〈10月18日締切・申込必要〉
大阪は淀川河口に広がる海岸平野に位置しています。大阪の地盤となっている軟弱な平野地下に分布する厚い地層がどのようにして形成されたのかを紹介し、地震災害との関連について、大阪府が行った地震動解析の結果なども交えながら解説します。
日時:11月 1日(土) 午後3時~午後4時30分 場所:自然史博物館 講堂
定員:250名
講師:三田村宗樹氏(大阪市立大学理学研究科 准教授)
③「地震-3.津波とはどういうものなのか?」 〈申込不要〉
地震の際に起こる津波は、地震の揺れよりもはるかに広範囲に被害を及ぼします。2003年のスマトラ沖地震津波が記憶に新しいですが、日本でも過去から多くの被害を受けてきています。津波とはどのようなものなのかを解説し、日本で行われている津波対策について紹介します。
日時:12月 6日(土) 午後3時~午後4時30分 場所:自然史博物館 集会室
講師:中条武司学芸員(第四紀研究室)
3.地震体験や展示ツアー
①「起震車で地震を体験してみよう!」 〈申込不要〉
大阪市消防局の地震体験車(起震車)で、地震の揺れを体験します。
日時:11月 1日(土)、2日(日)、12月6日(土)、7日(日) 各日午前10時30分~午後3時30分まで(ただし午後0時から午後1時30分までは休憩)
場所:自然史博物館ポーチ(ナガスクジラの下)
参加費:無料ただし博物館常設展入館料または植物園入園料が必要
②子どもワークショップ「なまちゃんハカセと展示ツアー」 〈申込不要〉
会場の中の「なまちゃんキッズパネル」をキーワードに、ハカセが展示を紹介します。
※「なまちゃん」は地震展2008のキャラクターです。
日時:10月25日(土)、26日(日)、11月22日(土)、23(日) 各日午前11:00~、午後1:00~、午後3:00~
参加費:無料ただし地震展入場料が必要
場所:自然史博物館ネイチャーホール ※「なまちゃん」は地震展2008のキャラクターです
4.地震の実験
ジオラボ「ペットボトルで液状化を実験!」 〈申込不要〉
地震の時に土砂がぐしゃぐしゃになり、建物などに大きな被害をもたらす地層の液状化を、ペットボトルを使った簡単な実験で再現します。液状化や地震への理解を深めましょう。
日時:11月 8日(土)午後2時30分~午後3時30分 場所:自然史博物館ナウマンホール
講師:中条武司学芸員(第四紀研究室)
5.地震の野外観察
テーマ別自然観察会・活断層を歩くシリーズ7「上町断層」 〈11月18日締切・申込必要〉
上町断層は谷町のお寺が集まる上町台地の西縁に位置していて、大阪層群など古い地層を大きくずらしていることはわかっていますが、最新の活動時期や活動の周期など不明な点もあります。断層に関係する湧水や地形などを観察します。
日時:11月30日(日) 終日 雨天中止 場所:大阪市
講師:川端清司学芸員(地史研究室)ほか 定員:50名
参加費:中学生以上100円、小学生50円
[関連行事の申込方法]
往復はがき又は電子メール、自然史博物館ホームページからも申込できます。
(行事名、参加希望者全員の氏名、年齢(学年)、住所、電話番号、および返信用宛名を記入)
・宛先 〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-23 大阪市立自然史博物館普及係あて
・電子メール gyouji@mus-nh.city.osaka.jp(@を半角にして下さい)
・自然史博物館ホームページ http://www.mus-nh.city.osaka.jp/ 「イベント」欄より
投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 14:00 | この記事のみ表示

大阪市立自然史博物館では、関西自然保護機構、特定非営利活動法人 大阪自然史センター、社団法人 日本望遠鏡工業会と共催で、11月15日(土)、16日(日)の2日間、大阪市立自然史博物館において、「かんさい自然フェスタ2008」を開催します。
ここ数十年、日本各地でさまざまな自然保護上の課題が発生し、それに対する保全・保護を目指した運動が繰り広げられてきました。かんさい自然フェスタは、関西各地で自然保護上の課題に直面している方、大学などで関連の研究をしている方、そして自然に興味のある方と、自然保護についての情報を共有し、広く発信する場として企画しました。
関西の自然に関係する62団体が集まり、ブース出展によるハンズオンセッション、ワークショップショーケースといったフェスティバルのような楽しい企画を展開しつつ、ポスター発表による調査研究の発表や活動紹介、シンポジウムもあります。地域の自然保護活動を広く一般に知ってもらうと同時に、活動同士の横のつながりを作り、さらには大学などにおける研究成果を地域の自然保護活動にいかすきっかけになればと考えています。
11月15日(土)には、関東を中心にカエルの調査・保全活動を展開しているカエル探偵団から、長谷川雅美氏(東邦大学教授)をお招きして、招待講演会「カエルのきもちを忘れない」を開催します。
11月16日(日)には、自然保護レクチャー「開発から自然を守るには −開発計画への予防と対策−」を開催します。中瀬勲氏(兵庫県立大学教授)、角野康郎氏(神戸大学教授)、森誠一氏(岐阜経済大学教授)というそれぞれ自然保護の第一線で活躍しているお三方に講義をしていただきます。
また、鳥類イラストの第一人者、谷口高司氏(谷口高司鳥絵工房)による「タマゴ式鳥絵塾」の講習会も開かれます。本にもなっているタマゴ式鳥のイラスト法を、著者自身から手ほどきしてもらえる絶好の機会です。その他、自然環境の保全に関わるさまざまなシンポジウム、自然を楽しむワークショップやブース展示など、盛りだくさんの内容です。
詳しくはプレスリリース、webサイトをご覧下さい
主 催 関西自然保護機構、NPO法人大阪自然史センター、
大阪市立自然史博物館、社団法人日本望遠鏡工業会
協 賛 社団法人日本望遠鏡工業会、
オリンパス、ケンコー、コーワ、ツァイス、ニコン、ビクセン(各ブランド名称)
株式会社日本鳥類調査・Hobby's World、HOGA、株式会社文一総合出版、
谷口高司鳥絵工房、招き鳥の巣、ちくじん関西(環境部会)
期 間 平成20年11月15日(土)〜16日(日)
■■当日は関西文化の日となり、入館料は無料です。かんさい自然フェスタも無料でご覧いただけます■■
かんさい自然フェスタHP
PDF(festa2008press0926.pdf 188KB)
投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 13:59 | この記事のみ表示
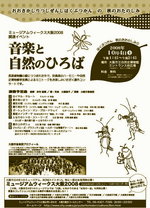 />
/>
自然史博物館では大阪市音楽団のご協力により10月4日、午後1時30分より「音楽と自然のひろば」を開催いたします。
大阪市音楽団は、国内屈指の交響吹奏楽団です。上質なブラスサウンドを、ミュージアムウィークス開催中の秋の一日、そろそろ秋風の吹き始めた長居公園で自然を感じながら、抜群のロケーションの中で音楽を楽しみませんか?
当日は会場の頭上にそびえる、ナガスクジラの骨格標本「ナガスケ」の、学芸員による解説ミニトークもあります。
また館内では、「鳴く虫巡回展」がこの日からスタート。耳でも楽しい自然史博物館の秋の一日をご堪能ください。
日時:10月4日(土) 午後1時30分~午後3時頃(予定)雨天決行
場所:大阪市立自然史博物館 玄関前ポーチ
対象:どなたでも参加できます
お申込:申込みは不要です、直接集合場所・会場へお越しください
参加費:無料(ただし、植物園入園料が必要)
大阪市音楽団
http://www.shion.jp/
ミュージアム・ウィークス
http://www.city.osaka.jp/yutoritomidori/culture/8on_03.html
自然史博物館トップ
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 11:38 | この記事のみ表示
鳴く虫は多くの歌にも唄われるように、古来より人の耳を和ませる風雅な響きであったとともに、都市の変化や開発による環境の変化を鋭敏に反映してくれる「環境のインジケーター」でもあります。そして、多くの昆虫アマチュアの心を捉えた存在でもありました。「バッタ・コオロギ・キリギリス大図鑑」は関西を中心に活躍する、プロアマを越えた直翅類研究者たちの業績の結晶ともいえます。今回の巡回展では、こうした鳴く虫たちの姿を、さまざまな形で楽しく伝えていきたいと考えています。
この巡回展は橿原市昆虫館(奈良)と日本直翅類学会が監修した基本パックをもとに、大阪、兵庫、滋賀、奈良にある6博物館がそれぞれ工夫し、標本等を使って、バラエティ豊かに展開する「成長する巡回展」です。特定非営利活動法人・西日本自然史系博物館ネットワークのもとで、「社会の中で自然史系博物館の機能を発揮する」という那須自然史基金の趣旨に添って各館学芸員の協力により実現されました。
大阪市立自然史博物館では当館から誕生した日本直翅類学会の豊富な標本、鳴声、虫かごなどの民具を中心に展示します。収蔵している関連標本や鳴声録音を活用し、博物館と学会との関わりも展示する予定です。また、大阪市立自然史博物館叢書シリーズ第4巻「鳴く虫」本も発刊の予定です。
ご期待ください。
大阪市立自然史博物館での会期は2008年10月4日(土)~11月3日(月・祝)、大阪市立自然史博物館 ・二階イベントスペースでの開催となります。http://www.mus-nh.city.osaka.jp/1attention/index.html常設展入館料のみでご覧いただけます。
西日本自然史博物館ネットワークによるプレスリリース(PDF)をダウンロード
投稿者: 大阪市立自然史博物館 日時: 10:48 | この記事のみ表示
検索
大阪市立自然史博物館
カテゴリー
- #おうちミュージアム (16)
- イベント情報 (151)
- テーマ展示・ミニ展示 (15)
- トリケラトプス展 (11)
- ホームページのお知らせ (20)
- 今月の自然史博物館 (9)
- 博物館からのお知らせ (447)
- ネイチャーホールの貸館イベント (2)
- 友の会からのお知らせ (13)
- 子どもワークショップ (10)
- 学校関係のみなさんへ (28)
- 書籍 (9)
- 特別展 (7)
- 2015年以前の特別展
- きのこのヒミツ (11)
- たまごとたね (10)
- のぞいてみようハチの世界 (8)
- ようこそ恐竜ラボへ! (9)
- スペイン奇跡の恐竜たち (12)
- ダーウィン展 (7)
- ホネホネ探検隊 (5)
- 世界のチョウと甲虫 (2)
- 世界一のセミ展/2007夏 (12)
- 世界最大の翼竜展 (5)
- 地震展2008 (12)
- 大化石展 (11)
- 大恐竜展 (13)
- 大阪湾展 (9)
- 新説・恐竜の成長 (13)
- 海はモンスターでいっぱい (7)
- 淀川展 (6)
- 発掘!モンゴル恐竜化石展 (9)
- 都市の自然 (8)
- きのこ!キノコ!木の子! (10)
- ノーベル賞受賞100年記念「アインシュタイン展」 (5)
- メガ恐竜展 (7)
- 大阪アンダーグラウンド (6)
- 大阪アンダーグラウンドRETURNS (1)
- 恐竜の卵 (5)
- 日本の鳥の巣と卵427 ~小海途銀次郎 鳥の巣コレクションのすべて~ (6)
- 氷河時代 (10)
- 瀬戸内海の自然を楽しむ (12)
- 特別展「大地のハンター展」 (4)
- 特別展「昆虫」 (9)
- 特別展「植物 地球を支える仲間たち」 (3)
- 特別展「毒」 (1)
- 生命大躍進 (10)
- 知るからはじめる外来生物 (7)
- 石は地球のワンダー (8)
- 2015年以前の特別展
- 特別陳列 (10)
- ヘルマン・ヘッセ昆虫展 (3)
- 深海生物の写真展 (2)
- 研究成果 (11)
- 自然史博物館YOUTUBE (8)
月別アーカイブ
最近のエントリー
Movable Type 3.2-ja-2
