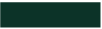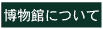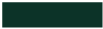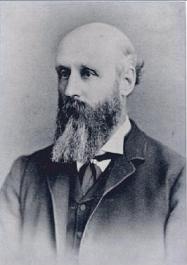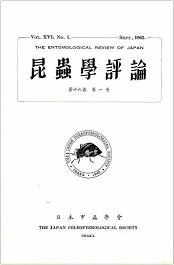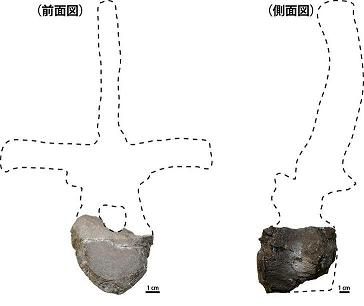10月1日(土)、特別展「氷河時代」の来場者数が2万人を突破しました。
記念すべき2万人目のお客様は、大東市からお越しの尾上慶明くん(2才)とそのご家族。
大阪市立自然史博物館の谷田一三館長から、記念品として特別展の解説書とオリジナルグッズのナウマンゾウ アルミマウンテンボトルが贈られました。
ご家族の方は「自然史博物館には初めて来ました。(慶明くんが)大きくなったらまた連れて来たいです。」と話してくださいました。
特別展「氷河時代」は、10月16日(日)まで開催中です。
皆さまのご来場をお待ちしております!
特別展HP
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/tokuten/2016hyougajidai/