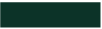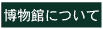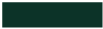好評開催中の特別展「発掘!モンゴル恐竜化石展」の入場者数が本日10万人を突破しました!

10万人目は尼崎市からお母さんの礼(あや)さんと一緒に来場した小学4年の柿田伊吹(かきた・いぶき)君でした。タルボサウルスのフィギュアなどの記念品が贈られました。
ティラノサウルスやプテラノドンが好きという柿田君は、モンゴルでこれほどたくさんの恐竜が見つかっていることを初めて知ったといい、「タルボサウルスの子どもの化石と大人の化石を見比べたら面白かった」と話してくれました。
特別展は6月2日までとなっています。是非お見逃しのありませんよう。
ゴールデンウィーク中の5月6日(月・祝)は開館し、翌5月7日(火)が振り替え休館となります。
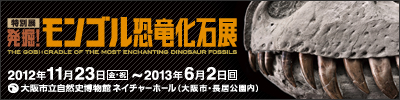
http://www.gobidinosaur.com